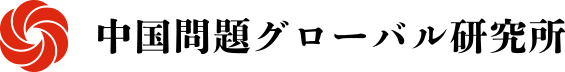返り咲くトランプ
ドナルド・トランプの2度目の大統領選勝利について、歴史家たちは今後何十年にもわたって議論し著述することになるだろう。「もしも」を考え始めたらキリがないが、そもそもバイデンは立候補すべきだったのか?後任候補の指名はカマラ・ハリスでよかったのか?あの瞬間にトランプが振り向かず、暗殺者の銃弾がかすめるだけでは済まなかったら?トランプが既決重罪犯として初めて国の最高職に選出されたという事実は確かに問題ではあるだろうが、犯罪歴がないことが米国大統領になるための必須条件ではない。実際、2016年の選挙では、有権者はトランプがポルノ女優のストーミー・ダニエルズと関係を持っていたことを知りながら彼に投票している。ならば、彼女への口止め料支払いのために事業口座を偽造した程度のことを今さら問題視するだろうか?
共和党は大統領選で勝利し、上院、下院の過半数を制して完勝した。一方、トランプがハリスに勝利したとはいえ、得票率が50%をわずかに下回ったという事実は注目に値する。無所属の候補者のうち得票率が最も高かった候補が約1.6%を獲得していることからも、トランプや共和党が主張するような圧倒的勝利ではなかったことが分かる。アメリカ国内の分断は4年前と8年前にも浮き彫りになったが、その後深刻化する一方だ。アメリカ国外はもとより、国内にいる人々でさえ、この現実に救いを見出す手立ては見つけられそうにない。
分断はあれども、現実としてトランプは勝利した。民主党の指導者たちも民主党寄りの評論家たちも、トランプにならって選挙が盗まれたと主張し、「大嘘」をついて見苦しい姿をさらすことはなかった。彼らは、かつてトランプが投票日の夜に行ったように、選挙結果の確定前から「大規模な選挙不正」を主張することもない。トランプが明確に、ただし僅差で勝利したことで、危険な事態は回避されたと言えるだろう。仮にトランプが敗北していれば、2021年1月6日にワシントンDCの議事堂に支持者たちが押し寄せたときよりもさらに過激な暴言を吐いていたに違いないからだ。
今後の動き
世界中のあらゆる国が、「トランプ2.0」のもとで次に何が起こるか神経をとがらせている。「アメリカ第一」を掲げるトランプは、同盟や同盟国を重視する気配がない。トランプにとっては何もかもが取引であり、すべての国がその対象だ。中国に対する新手の大型関税もあり得るだろう。バイデン大統領は中国に対する制裁と関税を継続、強化したが、トランプはメキシコとカナダに対してもすでに、就任初日に25%の関税を課すと予告している。これら国との現行の貿易協定は、自身の大統領施政時代にUSMCAの下で取りまとめたはずだが、当の本人は忘れてしまったのだろうか?
こうしたことは前回経験済みだという意見もある。世界は第一次トランプ政権を乗り切ったが、今回は何が違ってくるのか。トランプは本質的に、協調的政策や効果的政策を重視するタイプの人間ではない。その極端に過激なレトリックを敢えて政策と呼ぶとして、これについて不安に思うのは杞憂である。なぜなら、トランプ流のカオス的な政権運営のスタイルに加え、支持者や任命した人物間での内紛が続けば、結果として深刻なダメージが生じることはないと予想されるからだ。第二次トランプ政権は無秩序を極め、最終的にはエンターテインメントと化すだろうというのが最も楽観的な見方だ。
そう、トランプには「エンターテイメント」という言葉が相応しい。トランプを支持する有権者の多くは彼を成功した実業家だと思っているが、そのイメージはリアリティ番組『アプレンティス』(The Apprentice)によって作られたものだ。1980年代を通じてトランプは多数のカジノやリゾートを経営し、結果、立て続けに破産して多数の労働者や業者への未払いが残った。常に実物よりも大きく見えがちな、まさに「アメリカらしい」人物ではあるが、ビジネスの成功という点では実際それほどではなかった。ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズ、ウォーレン・バフェット、ジャック・ウェルチといった現代アメリカの偉大なビジネスリーダーたちとトランプを同列に扱う者などいないだろう。
ならばトランプは実際に何をするというのか?彼は何をしたいのか?そしてその政策を実行するにふさわしいチームを本当に擁しているのか?前回も今回も明らかなのは、トランプ政権というものはまるで中世の宮廷で、有能で経験豊富な政治家や専門家で構成される近代的な政権とは異なることだ。トランプがさまざまな役職に据えた人々については、すでに一部で疑念を生じ、実際に懸念の種となってもいる。最初に指名した司法長官、マット・ゲイツは未成年者の性的人身売買や未成年者との性行為の噂が絶えなかったため、指名発表からまもなく辞任を余儀なくされた。疑惑が証明されたわけではないが、このような人物を政府の最高法務職に推薦しようという考え自体、信じがたいことだ。他の候補者たちはそこまで酷くはないが、やはり安心とは程遠い。国家情報長官に指名されたトゥルシー・ギャバードは、まるでロシアの操り人形のようだ。また、軍のトップには元テレビ司会者で元軍人のピート・ヘグセスが指名されている。いずれの人物もこれほど大規模で複雑な組織を運営した経験はなく、トランプが、自分に都合の良いことを語る人物を選んでいることがよく分かる。トランプにとっては、国の重要機関の運営トップを務めるにはテレビのご意見番で十分なのだ。もう一つ注目すべきは、ロバート・F・ケネディ・ジュニアの指名である。保健省長官に就任することになるが、長年ワクチン陰謀論を唱えており、このような役割にはまったく相応しくない人物である。その他についてはさほど物議を醸すものではない。トランプへの忠誠と、トランプ路線の徹底を重要視しているにすぎないからだ。そのなかで読めないのが、イーロン・マスクの役どころである。トランプが「偉大なるイーロン・マスク」と呼ぶ彼は、資金をつぎ込んでアメリカ権力の中枢に入り込み、今のところトランプの応援団長的な存在となっている。テスラ社もスペースX社も政府からの契約や助成金によって多大な恩恵を受けてきたが、彼はいまや政府効率化省(Department of Government Efficiency、DOGE)の共同責任者に指名されている。ただしこれは実際には省ではなく、政府支出の2兆ドル削減を目指す諮問機関というべきものである。肥大化した省庁のスリム化、不要な規制の撤廃、税法や事業規制の簡素化は必要であり、多くの人々にとって魅力的なことは確かだ。しかしトランプとその側近たちは効率化という名目で、消費者の保護や権利など多くのものを切り捨てようとしているかに見える。
いかに対応すべきか
多くの国々はトランプの敗北を期待していただろうが、彼は勝利した。希望は無に帰し、トランプが公約を実行しないことにも期待できない。イエスマンばかりで構成されるこの「宮廷」が混乱し、トランプはほとんど何も成しえない可能性もあるが、それを当てにするわけにもいかない。むしろ、各国はトランプと積極的に関わり、対応策を講じる必要があるだろう。取るべき対応は国によって異なるが、いくつか例を挙げて説明しよう。
ウクライナはすでにロシアとの協議について譲歩を見せ、激しい交戦を停止している。トランプは24時間で戦争を停止できると豪語しているが、その真意は明らかにしていない。ウクライナへのさらなる支援を停止すれば、確かに戦争は止まるだろう。しかし、それではプーチンに明確な勝利をもたらし、旧ソ連領へのさらなる進出を招くことになる。トランプの戦争終結の狙いは、アメリカの財政負担を減らすことであり、ウクライナ国民の安全保障や領土保全、プーチンへの制裁などといった意識は微塵もない。この状況を踏まえ、ゼレンスキー大統領は非現実的ともいえる提案をした。すなわち、戦争を停止し、ウクライナ全土をNATOの安全保障下に置き、現在占領されている領土については将来的な外交交渉に委ねるというものだ。実現の可能性は低く、トランプもプーチンも到底同意するとは思えない。それでも、ゼレンスキー大統領は米国の支援方針の変化を理解し、少なくとも合意に向けて前進する意思があることを示す必要がある。
これと関連するがまた別の問題として、既存のNATO加盟国による防衛費の増額がある。第一次政権中にもトランプはこの問題を強く提起していたが、NATO加盟国の多くは防衛費の増額を遅々として進めていない。欧州本土で現在、激しい戦闘が繰り広げられていることを考えても、欧州の加盟国にとってこの問題がいまだに優先課題になっていないというのは信じがたい。防衛費以外では、予告されている関税強化がEUのさまざまな商品やサービスに打撃を与えることになるだろう。金融規制や環境・気候政策の国際協調も、トランプの周囲でより極端な声が高まることで壊滅的な打撃を受けるおそれがある。EUは、初動対応として報復関税を課すだろうが、それによってEUに対する措置はさらに極端なものへと転じかねない。経済的苦境に置かれている英国は、EUよりもさらに厳しい状況にある。トランプの母親はスコットランド人だが、貿易問題での配慮など期待できない。EU離脱後の英国はいまや世界的影響力をほとんど持たない中規模の経済圏であり、長い歴史を持つ米国と英国の特別な関係もトランプは意に介さないだろう。
アジアには、台湾を巡る安全保障上の明確な懸念と、中国による軍事行動の脅威の高まりという問題がある。アメリカは台湾と共にあるとバイデンは明言したが、果たしてトランプはそのような約束をするだろうか?トランプは習近平への称賛をしばしば口にしており、ウクライナへの支援の行方によってはこの地域にも重大な影響が及ぶ可能性がある。
一方、貿易に関しては、中国は最悪の状況を迎えることになりそうだ。現時点で60%の関税が予告されているが、さらに上乗せされることは確実だ。国務長官に指名されたマルコ・ルビオは対中強硬派として知られている上、トランプの大統領退任以降、中国関連の事柄への非難は党を問わず増加する一方である。中国に関しては、トランプの「偉大なるイーロン・マスク」が最も注目される存在と言える。テスラは中国に多額の投資を行っており、イーロン・マスクは中国指導者たちの歓心を得ようと何度も試みてきた。その彼がどこまで妥協するかが注目される。
いささか皮肉なことではあるが、ベトナムは関税合戦の渦中に置かれる可能性がある。というのも、トランプの「デカップリング」政策により、中国製造業の多くがベトナムに移転または進出し、トランプの退任以降、対米貿易赤字が急増しているためだ。
日本については、トランプの怒りの矛先が地域内の他の標的に向けられているため、完全なターゲットとなることはないかもしれないが、彼は円安を不公平と見なすであろうし、日本に対してもEU諸国と同様に防衛負担増額を要求してくることは間違いない。
今後10年間の暗く過酷な未来予想図は簡単に思い描くことができる。「トランプ2.0」はそれを決定づける上で重要な役割を果たすことになるだろう。アメリカが他国への関与を避けて無関心を貫けば、自国民を抑圧し他国を侵略する独裁者たちが続々と登場することになる。仮に「トランプ2.0」が描き出す最悪のシナリオが実現しなかったとしても、各国が内政を強化しなければならないことに変わりはない。サイバーセキュリティを含めた防衛費、エネルギー安全保障、国内経済の課題、移民、年金改革、人口動態に応じた医療サービス改革など、取り組むべき問題は実に多岐にわたる。これらすべてにおいて、個人的な利益よりも国家の利益を優先して行動する真摯な人材が求められる。「古き良き時代」を懐かしんでも無駄なことだ。世界的な金融システムや国際機関の緊迫感は、平和だった過去とは比べ物にならないほど高まっている。現状維持のためアメリカに頼ることは、もはやできない。居丈高な中国、ロシアによる侵略と虚偽情報、気候変動と環境への影響。そして数百万人が移住を余儀なくされる一方で、多くの先進国が高齢化に苦しみ、人口動態の変化への対応に苦慮している状況に対処していくには、巧みなリーダーシップが不可欠だ。そのようなリーダーやリーダー候補を擁する国がどれほど存在するのかは、まったく不透明である。
カテゴリー
最近の投稿
- Old Wine in a New Bottle? When Economic Integration Meets Security Alignment: Rethinking China’s Taiwan Policy in the “15th Five-Year Plan”
- イラン「ホルムズ海峡通行、中露には許可」
- なぜ全人代で李強首相は「覇権主義と強権政治に断固反対」を読み飛ばしたのか?
- From Energy to Strategic Nodes: Rethinking China’s Geopolitical Space in an Era of Geoeconomic Competition
- イラン爆撃により中国はダメージを受けるのか?
- Internationalizing the Renminbi
- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する
- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ
- 記憶に残る1月