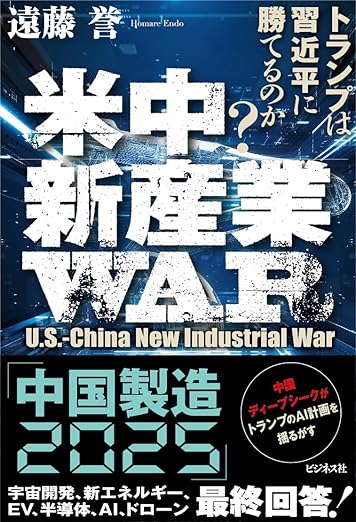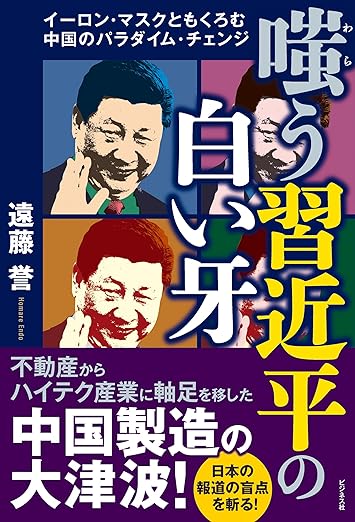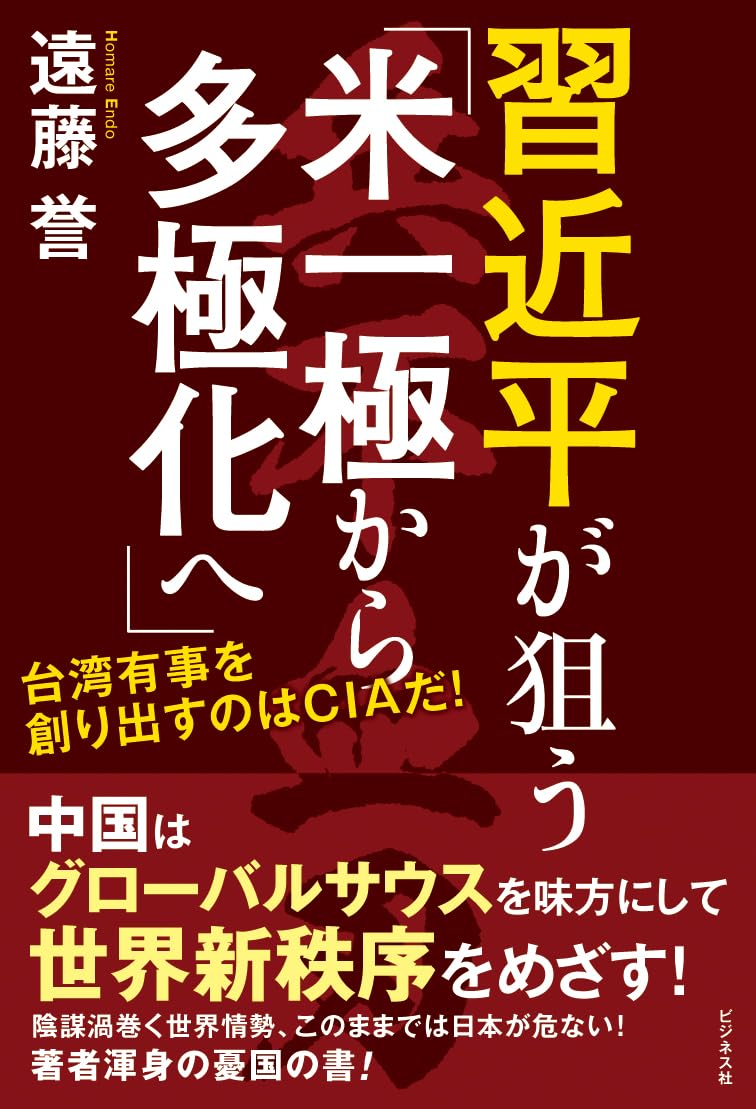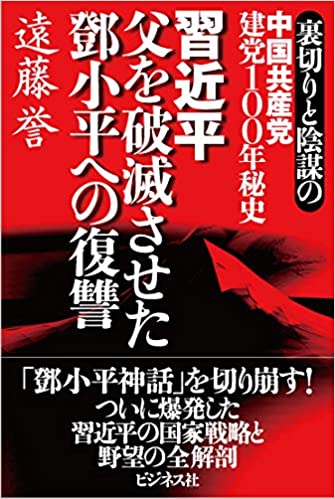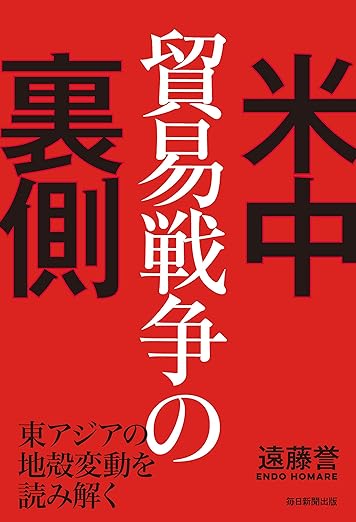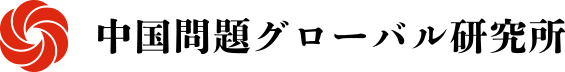10月16日から第20回党大会が始まるが、習近平三期目は既定路線としても、習近平がなぜ三期目を目指すのかを正確に分析しないと中国政治の現在と未来を見誤ってしまう。それを避けるために考察を試みる。
◆多数決議決のため政治局常務委員会委員数は「奇数」が原則
中国共産党全国代表大会(党大会)は5年に一回開く決まりになっているが、今年10月16日から第20回党大会が北京で開催される。9千万人以上いる党員の間で選挙ばれた2千人強の党員代表によって構成され、その中から中国共産党中央委員会(中共中央)の委員約200人およびほぼ同数の候補委員を選出する。党大会閉幕後、第一回中央委員会全体会議(一中全会)を開催し、25名の中共中央政治局委員と「若干名」の政治局常務委員、および中共中央総書記(党のトップ)が選ばれる。
胡錦涛時代(党:2002年~2012年、政府:2003年~2013年)、政治局常務委員は9人だったので、筆者は彼らを「チャイナ・ナイン」と命名して『チャイナ・ナイン 中国を動かす9人の男たち』という本を2012年3月に出版した。しかしその年の11月に第18回党大会が開催され、習近平が中共中央総書記に選ばれると、「9人」が「7人」となっていたので、今度はその7人を「チャイナ・セブン」と名付けた。
「若干名」と書いたのは、このように、蓋を開けてみないと何名になるか分からないからである。
いずれにしても常務委員会会議では多数決によって議事を進めていくので、「奇数」ということが基本になっている。もし偶数なら、賛否が半々に分かれたときに、総書記一人の意思で最終決定をすることになるので、独断の要素が入る。それくらい中共中央政治局常務委員会は多数決にこだわってきた。
あの「独裁」と呼ばれた毛沢東でさえ、文化大革命前まではこの原則を守っていた。
1958年に始めた大躍進が失敗した後、1959年に毛沢東は自ら「なんなら国家主席を降りてもいい」という類のことを周りに言うが、毛沢東としては「きっと周りが必死で引き留めるだろう」と期待していたところ、政治局常務委員会会議で多数決議決により「毛沢東の申し出」が認められてしまった。こうして劉少奇が国家主席に選ばれ、毛沢東は劉少奇を「国家主席の座から引きずり下ろすために」、1966年に文化大革命を起こしたほどだ。
したがって第20回党大会においても、この「奇数であること」を変える可能性はあまり大きくはない。
◆三期目を狙う習近平
今年特に注目すべきは、習近平が三期目に入るだろうということだ。
というのは、中共中央総書記および中共中央軍事委員会(中共中央委員会で選出)の主席に関しては任期制限が設けられていないが、「国家主席」に関しては憲法で「一期5年、最長二期10年」と決まっていた。
江沢民政権から「中共中央総書記と中央軍事委員会主席と国家主席」は「同一人物が担う」ことになったので、「国家主席」の任期が最大二期10年であるなら、自ずと党大会で決まる中共中央総書記と中共中央軍事員会主席の任期も、二期10年になってしまう。
ところが2017年の第19回党大会で党規約の中に「習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想」を書き入れ、その「新時代」の特徴の一つとして2018年3月における全人代(全国人民代表大会)で憲法を改正し、「国家主席の任期を撤廃」してしまった。結果、党大会で決める総書記も軍事委員会主席も、「二期10年」にする必要はなくなり、第20回党大会で、習近平は三期目の総書記および軍事委員会主席に選ばれてもいいことになったわけだ。すなわち、第三期目を迎えるということになる。
もし一中全会で習近平が三期連続で選出されれば、来年2023年3月に開催されることになっている全人代でも「国家主席」に選出されて、習近平政権の三期目が始まる。三期目があるということは、四期目も排除しないということになろう。生きている限り、すなわち「終身」ということも考えられないわけではない。
では、習近平はなぜそのようなことを目指すのか?
◆三期目を狙う最大の理由は「父・習仲勲を破滅させた鄧小平のへの復讐」
習近平が三期目を狙う最大の理由は、何と言っても拙著『習近平 父・習仲勲を破滅させた鄧小平への復讐』で書いたように、父の仇討ちである。
習近平の父・習仲勲は、鄧小平の陰謀により1962年に国務院副総理兼国務院秘書長など全ての職を剥奪されて、その後16年間も監獄・軟禁・監視生活を送らされている。なぜそのようなことが起きたかというと、毛沢東が習仲勲を可愛がって、後継者の一人にしようとしていたからだ。
というのも、1935年に毛沢東が蒋介石率いる国民党軍の攻撃を逃れて「長征」を続け北上した時、もう中国全土のどこにも共産党軍の革命根拠地がなくなっていた。唯一残っていたのは、習仲勲らが築き上げていた陝西省を中心にした西北革命根拠地だった。毛沢東が最終的に蒋介石に勝てたのは、ここに「延安」があり、延安を新たな「革命根拠地」として戦うことができたからだ。毛沢東は習仲勲に救われたようなもので、1949年10月1日に新中国(中華人民共和国)が誕生した後も、習仲勲ら西北革命根拠地を築いていた英雄たちを大切にした。野心の強かった鄧小平は、このままでは自分の将来がなくなることを恐れ、陰謀を図って習仲勲を失脚させたのである。
それさえなければ父・習仲勲は毛沢東の後継者として輝かしく活躍していただろう。
習近平の胸には、半世紀もため込んできたこの無念の思いが沸々と煮えたぎっていたはずだ。父の仇を討つためにも、人の何倍も中国という国家のトップに立っていようと思っているにちがいない。
これが習近平の核心にあることこそが最も重要であって、実は誰が常務委員になるかとか、誰が国務院総理になるかなどは、その事実の前には霞んでしまい、ほぼ、どうでもいいくらいに小さい。これが見えないと、今の中国の政治を正しく分析することはできないと確信する。
◆アメリカに潰されるわけにはいかないという中国の危機感
二つ目は習近平の内的要因ではなく、アメリカに潰されるわけにはいかないという危機感が習近平を三期目へと追いやっているという外的要因があるということだ。
あと数年で中国経済がアメリカ経済を追い越そうとしている。
そうはさせまいと、アメリカは半導体などを中心として中国への制裁を強化し、最近ではたとえば「半導体支援法」に関し、「資金を受けている企業は今後10年間、中国国内で先端工程施設を建設することはできない」という付帯条件を設けたり、またIPEF(インド太平洋経済枠組)により中国を排除しようと必死だ。
一方、台湾が独立を宣言しない限り、中国は平和統一しか考えていない。武力統一などをしたら台湾に強烈な反中分子を生んでしまい、統一後、共産党による一党支配体制が危うくなるからだ。
しかし平和統一だと中国経済は益々成長するので、アメリカはそれを潰すために何とか中国が台湾を武力攻撃してくれるように米政府高官を訪台させたりして中国と国際世論を煽っている。
米中覇権競争の真っただ中にたまたま差し掛かってしまった中国のトップ・リーダーとして、習近平以上に「紅い革命のDNA」を引き継いだ強力なリーダーはいない。今そのリーダーを交代させるわけにはいかないという切羽詰まった事情が中国にはある。
◆習近平以外ではダメなのか?
他の人物ではアメリカに勝てないのかという見方もあるだろう。
皆無ではないが、習近平ほどの「紅い革命のDNA」を直系で持っている人間はいない。習近平が中国共産党の「初心」と「延安」を強調するのは、父・習仲勲が延安を中心とする西北革命根拠地で1935年に毛沢東を助けたからだが、もう一つ、毛沢東思想にこだわるのは、どの指導者も「第二のゴルバチョフになってはならない」という思いがあるということを見逃してはならない(参照:9月5日のコラム<中国共産党「第二のゴルバチョフにだけはなるな!」>)。
アメリカの(甘い)話に乗っかれば、ソ連が崩壊したように、共産中国も崩壊する。
崩壊させてなるものかと、習近平はつぎつぎと手を打っている。
たとえば、『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第二章の五(中国に対してSWIFT制裁はできない――なぜなら世界貿易を支配しているのは中国だから)に書いたように、世界190ヵ国のうち128ヵ国が中国を最大貿易国としている。その128ヵ国のうち90ヵ国がアメリカの2倍以上の貿易を中国と行っている。
また9月1日のコラム<米中貿易データから見える「アメリカが常に戦争を仕掛けていないと困るわけ」>で書いたように、中国は製造業において圧倒的優位に立っており、また国際エネルギー機関(IEA)によると、中国は太陽光パネルのすべての主要製造段階で80%以上の市場シェアを占めているとのこと。
加えて、今年9月7日に習近平は「全面深化改革委員会」第27回会議を開催して「核心的技術を向上させるべく新型挙国体制で取り組め」という指示を出し、「社会主義体制の特徴を発揮して力を集中させ、国家事業として科学技術のイノベーションを促進し科学技術のレベルアップを国家戦略の主戦場とせよ」と強調している。
アメリカは中国政府が市場に介入してくることを自由競争への挑戦だとして非難してきたが、アメリカ自身が半導体分野などに国家が介入し、他国(中国など)への制裁も含めて国家事業として特定分野の産業への支援をしているので、「国策」として動いているのは米中どっちもどっちという感はぬぐえない。
その際、自由な発想だけが産業競争力を高めるのかというと、必ずしもそうではない。ひところアメリカのシリコンバレーが栄えた時代とは異なり、現在は次の段階に入っていて、他国への制裁という排除理論で国際関係を築いているバイデン政権よりも、「人類運命共同体」を外交スローガンとする習近平政権の方が、より多くの発展途上国の賛同を得ている。
たとえばアフリカ諸国はロシア制裁に加わっておらず、むしろ習近平政権と利害を一致させているし、アメリカの裏庭である中南米においても中国の存在感が増している。
西側からは「強硬路線」と批判されても、こういった強烈なリーダーシップを発揮する人物が、いま中国にいないとアメリカに呑み込まれ、第二のゴルバチョフになり兼ねないのである。
日本の中国研究者は権力闘争と言いたがるが、そんな視点を持っていたら、中国政治の現在と未来を見誤るだろう。
なお、「チャイナ・ナイン」の時は江沢民が胡錦涛政権に刺客を送り込み、激しい権力闘争が行われていた。しかし「チャイナ・セブン」になった習近平体制では、権力闘争をする対等な相手はおらず、胡錦涛と習近平は腐敗撲滅運動に関して徹底して協力している(2012年の第18回党大会で、二人とも「腐敗を撲滅させなければ党が滅び国が亡ぶ」と誓い合っている)。
腐敗を撲滅させる目的は、腐敗の巣窟と化した軍の腐敗体制に斬り込み、軍のハイテク化を図ることによって「強軍の夢」を実現させるためであり、「中国製造2025」というハイテク国家戦略を実行することによって、アメリカに勝つことが目的だ。
それを見誤ると日本の国益を損ねる。注意を喚起したい。
カテゴリー
最近の投稿
- Old Wine in a New Bottle? When Economic Integration Meets Security Alignment: Rethinking China’s Taiwan Policy in the “15th Five-Year Plan”
- イラン「ホルムズ海峡通行、中露には許可」
- なぜ全人代で李強首相は「覇権主義と強権政治に断固反対」を読み飛ばしたのか?
- From Energy to Strategic Nodes: Rethinking China’s Geopolitical Space in an Era of Geoeconomic Competition
- イラン爆撃により中国はダメージを受けるのか?
- Internationalizing the Renminbi
- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する
- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ
- 記憶に残る1月