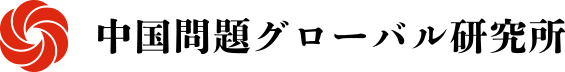「中国を永遠に国際社会の外に置いておくことはできない。孤立が続けば、幻想を肥大させ、敵愾心を募らせ、近隣国の脅威となるからだ。」
リチャード・ニクソン、1967年
「怒れる孤立」
リチャード・ニクソン大統領がこの言葉を書いた当時、世界情勢は、現在とはまったく異なっていた。 米国は、泥沼化したインドシナでの戦争から抜け出せず、米ソ冷戦の影響は世界中に波及しており、中国においては、最終的にその物理的な遺産の多くと数百万人もの国民の命が失われることになる文化大革命が始まっていた。 中国は、人口こそ世界1位であったが、世界経済における存在感は小さく、台北の国民党政府が正統な中国代表権を有する政府と認められていたため、中国の外交官は世界のほとんどの首都から締め出されていた。
ニクソン大統領とヘンリー・キッシンジャー国家安全保障問題担当大統領補佐官は、中国の国民に民主主義と普遍的価値観を拡げるという聖戦的な意図ではなく、ソ連封じ込めのための世界規模の地政学的ゲームの一環として、対中戦略そして中国との関わり方を決めていた。 ニクソンは、中国が「怒れる孤立」の状態にあると表現しており、彼とキッシンジャーのやり方には失敗点もあったにせよ、当時の米国の中国に対するアプローチや関わり方は、現在までに多大なメリットをもたらしており、特に中国国民にとっては、近代史上で最も健康で、食料に恵まれ、金銭的に裕福な生活が実現することになった。 しかし現在、怒れる孤立は、妥当な表現であり憂慮すべき問題となっている。
武漢で珍しい呼吸器感染症の最初期の患者が記録されてから約2年が過ぎ、COVID-19は、最初に感染が始まったこの国を除く世界中で大流行した。 感染拡大の初期段階における対応、そしてその後の情報開示や透明性に関連した問題について、中国が大きな批判にさらされるのは当然のことである。 武漢の研究所で実際に何が起きていたのか、答えを知りたいと願っても、おそらく判明することはないだろう。 中国共産党の指導部は、ウイルスの起源、そして誰が何をどの時点で知っていたかという疑問に対して、否認とごまかしを強め続けてきた。 一方で、翌1月末には、中国はウイルス根絶を目指すことを決め、COVIDゼロ戦略に基づき、わずか1名であっても陽性者が見つかれば、国民に厳格な制限を課した。 その後、東アジアのいくつかの国や、よく知られるところではオーストラリアとニュージーランドも同様のアプローチをとった。 仮にすべての国がこうした厳しい制限を採用していれば、新型コロナウイルスのパンデミックがたどった経緯は大きく異なるものとなっていただろう。だが、きわめて多様な統治形態や社会規範の国々で構成されるこの世界において、COVIDゼロのアプローチがあらゆる国で成功したはずだと考えることは、現実には不可能である。 注目すべきは、中国では、この厳格なロックダウン後に国内での規制が大幅に緩和され、過去18ヵ月間の大半において、人々がCOVID-19関連の制限とは無縁な日常生活を送ってきたという事実である。 自国の「バブル」の中での国民生活は、ほぼかつての日常に戻っているのだ。
ただし、新型コロナウイルスの性質や深刻さがほとんどわかっていなかった流行当初であれば意味があったやり方は、今日ではもはや通用しなくなっている。 感染力の高いデルタ株への変異が起き、さらに重要な点として、効果的なワクチンが広く接種可能になったことで、パンデミックに対するアプローチをコロナウイルスとの共存へと転換させることも可能になり、現に世界の大半の国ですでにそうした方向転換が見られる。 そうした動きがどの国でも一様ということはなく、死亡者数や感染者数をどこまで許容できるかという問題になると、国ごとにかなりの違いがある。 シンガポールのウィズコロナ政策は英国のそれと大きく異なるように見えるが、両国とも、前に進むこと、そして、かつての日常に戻る代わりに、国民生活を全面的に左右する要素としてではなく生活の背景の一部としてCOVID-19を扱うやり方に戻ることが必要だと、十分に理解している。 ニュージーランドでさえ、ゼロコロナのアプローチはもはや理にかなっていないという認識に至っている。それにも関わらず、中国の指導部には、より共存的な姿勢に移行する兆しは見られず、今後数年間は、共存を目指す可能性は低い。
遠のく往来再開の時期
中国はこれまでに国内で開発・生産したワクチンの接種を22億回以上完了しており、このこと自体は際立った実績と言えるが、現実としてこうしたワクチンの有効性や感染防護力がどの程度であるかは不確かである。 初期の臨床試験データは乏しく、一部では矛盾も見られた。そして、中国国内では意味をなすだけの大規模な感染流行は起きていないため、現在も国民の多くが、COVID-19を経験していない状態である。 中国は、新型コロナウイルスワクチンの相互承認を要求しているが、中国国民のワクチン接種状況を理解するためのデータは事実上存在せず、そうしたデータを集めるのも不可能である。 したがって中国が海外との往来再開に意欲的でないのは、おそらく驚くにはあたらない。 だがこのことは、考慮すべき側面のひとつに過ぎない。 他のあらゆる事柄と同様に、何よりも大きいのは政治の問題である。 初期段階での失敗の後、中国共産党はゼロコロナの成功を、国民に対する国威発揚の手段として利用してきた。 国内において封じ込めがうまくいったのを、他の多くの国の明らかに高い死亡者数や失敗例と対照させながらアピールしてきたのだ。 それだけではなく、COVID-19の起源は中国にはなく、中国はパンデミックの犠牲者であるというありえない他国への非難を拡散し続けている。 この状況で中国は、現在の成功のイメージを損なうことなく、よりウイルスと共存する社会へと、はたしてどのように移行するのだろうか? 国産ワクチンの有効性は低いか中程度である可能性が高いこの国では、いかなるウィズコロナのアプローチも、感染者数と死亡者数の劇的な増加を招くと思われる。 国家が検閲体制をとっていても、携帯電話の普及率の高さを考えると、感染流行を国民の目から隠すことは不可能であろう。
国内でのイメージ低下を避けたいと願う一方で、注目される重要なイベントの数々が控えているため、少なくとも党指導部の考えとしては、コロナゼロと海外との往来の厳格な制限の継続は不可欠ということになる。 2022年2月の冬季五輪では、海外からの参加者数が厳しく制限され、到着後も常に監視を受けることになる。 さらに重要なイベントが、2022年後半の第20回党大会だ。奇蹟的な出来事でも起きない限り、同大会において、習近平党総書記が5年間の任期の3期目を迎えることが決まるだろう。 習氏の権力は、国家元首としての役割ではなく、中国共産党の最高指導者としての役割に起因している。 党大会は何年もかけて準備・計画され、彼にとっては、いかなる出来事(とりわけ新型コロナウイルスの流行)による妨害も許されない政治的日程の頂点なのである。 2020年3月の全国人民代表大会がCOVID-19により延期を余儀なくされたことを思い出してほしい。こうした事態は、今回の党大会においてはあってはならないのだ。 すなわち、これから少なくとも丸1年は海外との往来が制限されることになる。さらには、万事が計画通りに進むのであれば、そのわずか数ヵ月後の3月には国を挙げての壮大な人民代表大会が開かれる。それならば、少なくともその時期までは待つべきだという考え方になるだろう。 この対外孤立のタイムラインについて注目すべきは、中国の政治的な思惑において、それが大きな位置を占めていないという点だ。 2023年3月までに中国が世界への扉を開放する準備を整えているのだとすれば、自国に課した孤立が3年間続くことになるが、往来制限がさらに延長される可能性や、また、コロナ禍において多くの国が展開したきわめて厳格な隔離と電子追跡手段が中国国内で何らかの形で持続する可能性がないとは言えない。 国内のあらゆる活動をビッグデータで追跡することを理想的だと考える独裁的国家にとって、こうした統制手段を放棄する理由はないのである。
広東省は明らかに、入国時の隔離が当面なくならないと考えているようだ。 同省では、ホテルを利用した現在の隔離施設から離れた場所に、5,000人を収容できる専用の隔離施設を建設しており、まもなく完成を迎える。 また、中国本土との往来の確実な再開を目指しゼロコロナのアプローチをとる香港も、ここしばらくの間に、複数の隔離免除措置を廃止している。 本来は物、金、人が移動するハブであった香港は、難しい立場に置かれており、国際社会における役割の復活と同時に中国との往来再開を希望することはできない状況にある。 シンガポールは現在、国際的な往来再開のアプローチをとっているが、香港が希望する中国との往来再開とは正反対のやり方であるため、香港がこれを模倣することはできない。 香港にとって、中国との往来は、国際社会との関係よりも重要なのだろうか? 答えはおそらくイエスだが、この姿勢は、地域のハブと中国本土へのゲートウェイの両方の役割を担う香港にとっては、今後も重荷となり続けるだろう。 香港が、容易にアクセスできない場所のままであるならば、地域における役割や国際的な役割を果たすことはできなくなると思われる。今後も中国と同程度に入国が難しいのであれば、香港に行かずに直接中国に拠点を置けばいいのではないかと、海外企業は考えるはずだ。 香港が目指すところは、新型コロナウイルス対策について言えば、ほぼ一国一制度に等しいのだ。
グローバルリーダーとしての資質の問題
こうして孤立路線を継続した場合、今後数年間における中国の役割はどのようなものになるのだろうか? ビジネスの世界ではZoomやその他のプラットフォームを用いたバーチャルなやり取りが受け入れられているかもしれないが、社会のあらゆる局面において、人と人とが直接顔を合わせることの恩恵を過小評価してはならない。 コロナ後の世界は以前と同じではなく、制限や変化は今後何年も続くであろうが、それでも、人間が社会的な生物であることに変わりはない。 同僚間であれ、学生間であれ、政治指導者間であれ、中国社会のあらゆるレベルにおいて、対面によるやり取りが大きく減った状態は今後も続くと思われる。 中国はおそらく世界のリーダーの役割を担いたがっており、それを要求する場面も出てくるだろうが、その「リーダー」が動画のリンク先にしか現れないとしたら、いったい何が起こるだろうか? 習近平にとって、ローマでのG20首脳会議と気候サミットCOP26は、国際舞台に登場するのに理想的な場であったが、彼はそうしなかった。 他の外交官は現地に移動していたが、海外訪問に慣れているはずの習氏は、国を出ることを拒否したのだ。 このことは、何を物語るのだろうか? 国外にいる間に、政敵による陰謀が起きることを恐れているのだろうか? それともCOVID-19の感染を危惧しているのだろうか? あるいは、他国の首脳から、新型コロナウイルスの起源について情報を公開しなかったことを非難されると不安なのだろうか? 誰にも確かなことはわからないが、他国の首脳と顔を合わせなければ、国際社会での自身の評判や影響力をどのように高めればよいかを、知ることは難しくなる。
中国経済は、国内のロックダウンが終わった当初は好調であったが、現在は難しい状況に陥っている。 不動産セクターにおける過剰債務の問題は、特に中間層の経済を圧迫しており、国内消費も依然として低迷している。 国内経済のさまざまなセクターで抑制策がとられているとはいえ、海外からの投資機会は引き続き存在する。ただし、中国内外のビジネスパーソンが移動も対面でのミーティングも事実上できないのであれば、機会をフル活用する方法も、機会を部分的にでも開拓する方法も、見つけ出すことは困難である。 バーチャルでのつながりには、限界があるのだ。 さらに、COVID-19に起因する混乱によって顕わになったサプライチェーンの脆弱性に関しても、ビジネス界からの懸念が寄せられるはずである。 コロナ後の再建活動の一環として、企業はサプライチェーンの混乱から自社を切り離そうとすることが予想され、その結果として、中国は確実に困難を抱えることになると思われる。
昨年私はこのコラムで、この前例のない世界的なロックダウンの後で、どのような世界が出現するだろうかと問いかけた。 そのロックダウン後の世界に対する注目が徐々に高まっており、現状では、中国のビジネスパーソンや学生や旅行者は国内にとどまり、中国はきわめて熱心な海外からの旅行者以外に対しては閉ざされた国になると予想される。 このことからもわかるように、過去30年間の中国との関わりを指標として、今後の中国との関係を予測するのは難しい。 国外の我々は、中国が国際社会から距離を置き、幻想を肥大させ、敵愾心を募らせ、怒れる孤立へと逆戻りする事態にならないことを祈らなければならない。 気候変動対策に取り組み、将来またパンデミックが発生した時に適切に対応するには、中国の関与は不可欠だからだ。一方で、中国指導部の偏執的な態度を見ていると、当面の間は、そうした関与が進むことはなく、限定的なものにとどまると考えられる。
カテゴリー
最近の投稿
- 人民元の国際化
- Old Wine in a New Bottle? When Economic Integration Meets Security Alignment: Rethinking China’s Taiwan Policy in the “15th Five-Year Plan”
- イラン「ホルムズ海峡通行、中露には許可」
- なぜ全人代で李強首相は「覇権主義と強権政治に断固反対」を読み飛ばしたのか?
- From Energy to Strategic Nodes: Rethinking China’s Geopolitical Space in an Era of Geoeconomic Competition
- イラン爆撃により中国はダメージを受けるのか?
- Internationalizing the Renminbi
- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する
- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ