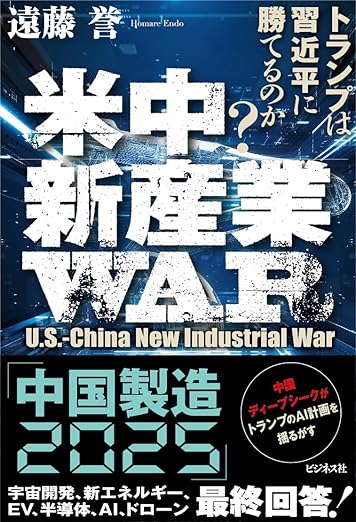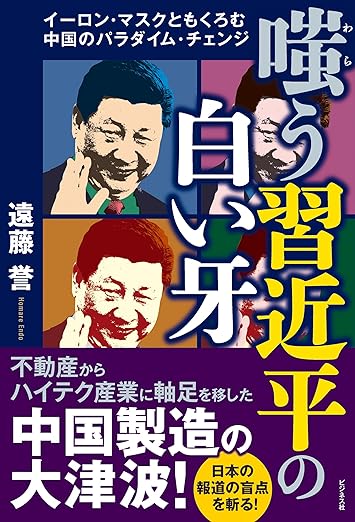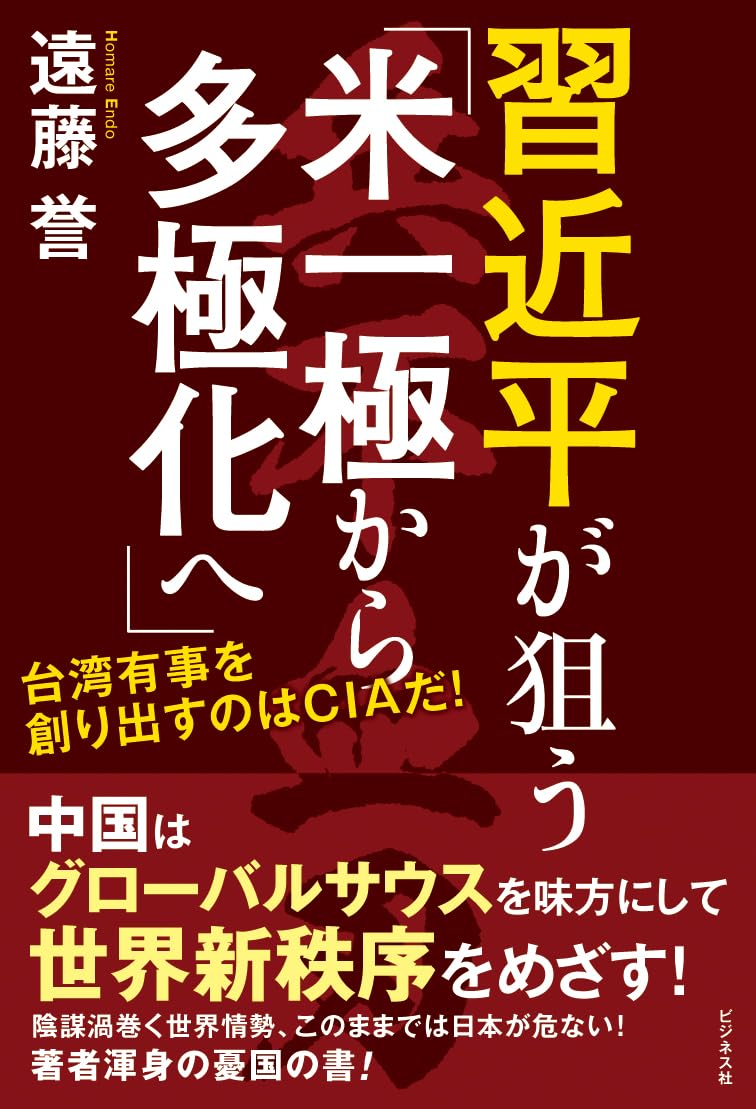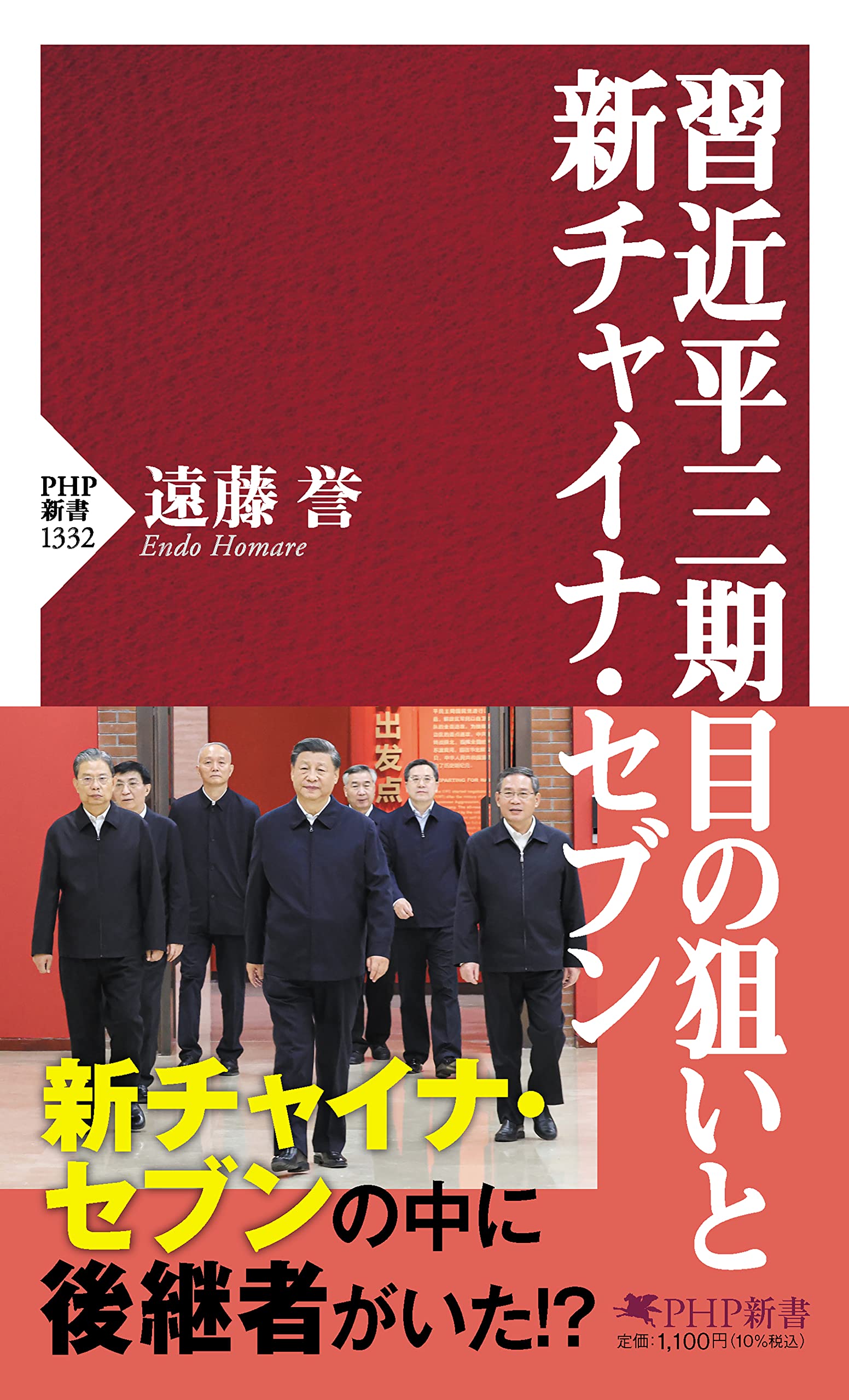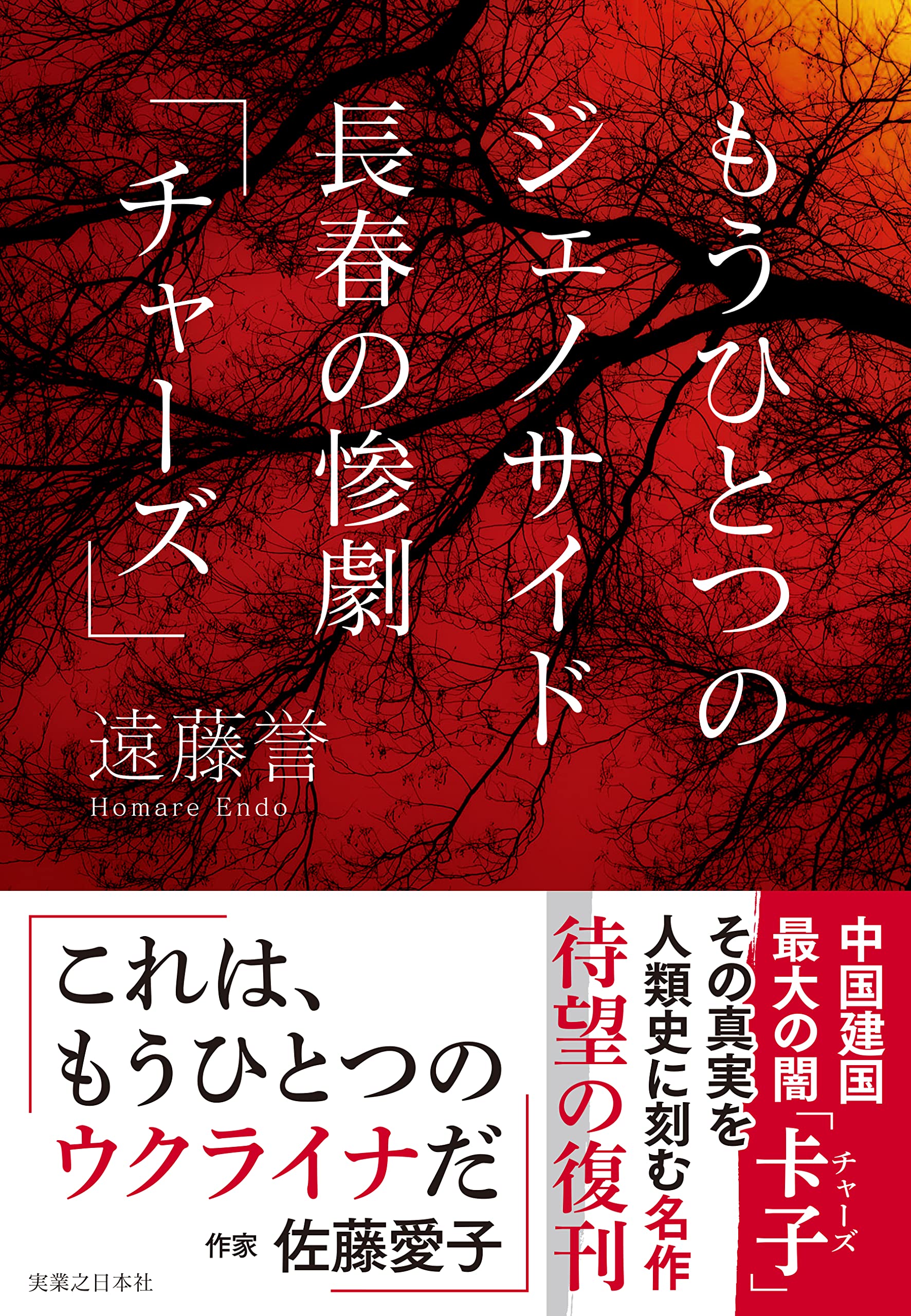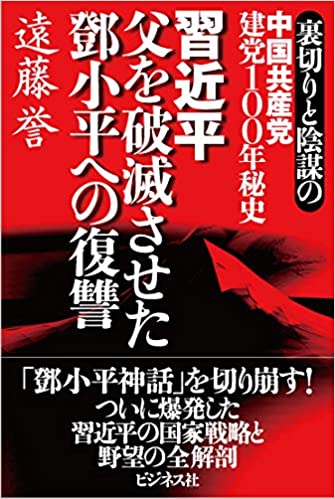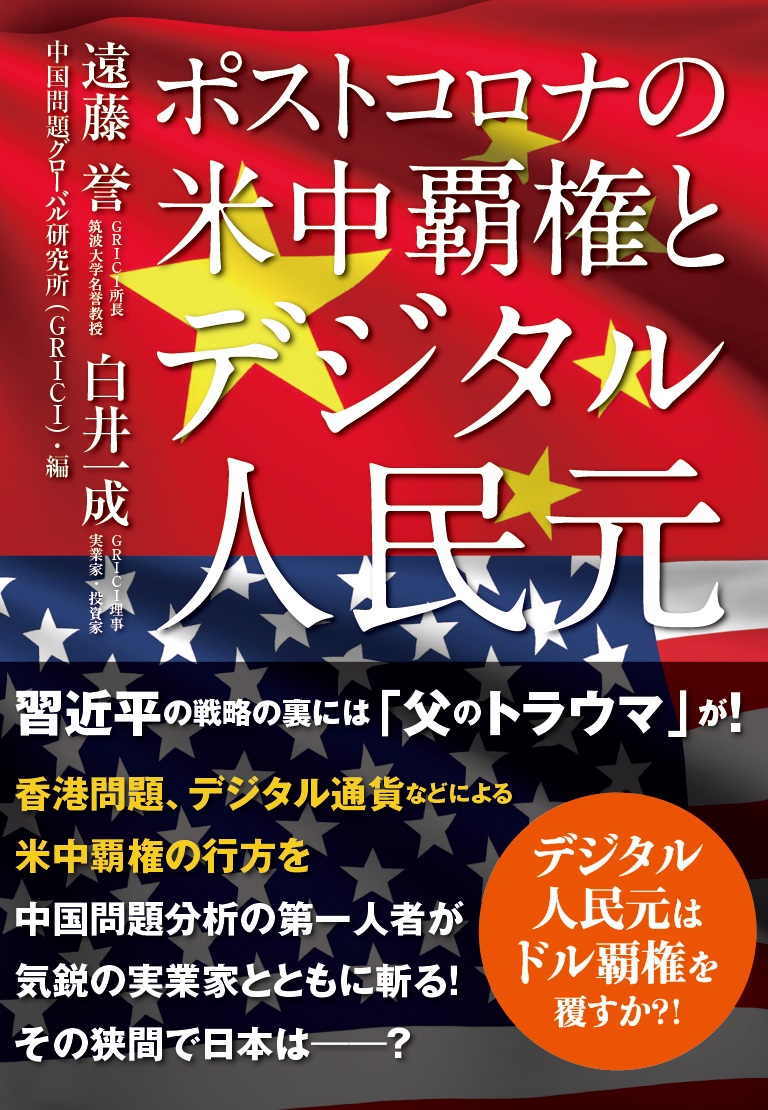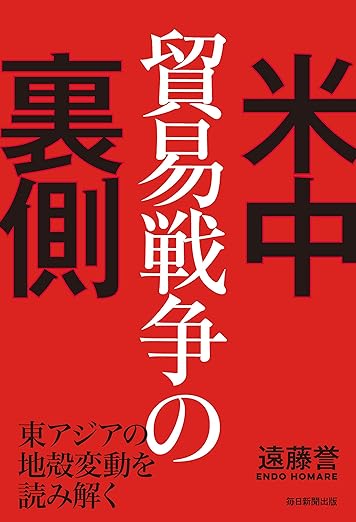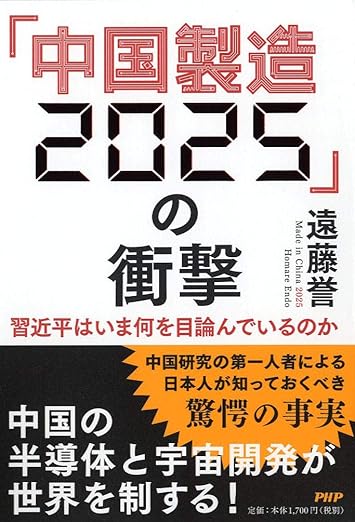トランプ大統領は8月6日、「海外から米国が輸入する半導体に約100%の関税を課す」と表明した。但し「米国内で生産を約束している場合あるいは米国内ですでに生産中の場合は、関税は課されない」という条件が付いている。
目的は「米国における半導体産業を復活させること」なのだが、海外からの輸入を喰いとめて、海外の半導体企業を(力づくで)米国に移転させ米国で半導体を製造させることによって「米国の半導体産業を復活させる」などというのは、いかにも邪道ではないだろうか。エンジニアがいるわけではないので雇用拡大にはつながらないし、エンジニアが育つまでには何年もかかる。高い人件費と「労働環境に不満があったらストをする」という文化の中で米国製造業が復活する見込みは小さい。
その一方で、中国製半導体は量的に世界の市場を席巻するだけでなく、質的にも中国の市場を奪いつつある。「半導体100%関税」は中国に有効かを考察する。
●米中逆転した「世界の半導体生産シェア」
まず、世界の半導体生産における米中のシェアの推移を見てみよう。
2024年11月15 日に最終更新された米商務省管轄のNIST(ニスト)(National Institute of Standards and Technology=米国国立標準技術研究所)のSemiconductors(半導体)データ(10年単位)によれば、1990年における米国の世界シェアは37%だったのだが、2020年には12%に落ち、2030年には10%に落ちるだろうと予測されている。したがって2025年予測値として11%を採用することは妥当だろう。
一方、中国の半導体生産の世界シェアは、2025年1月24日のVoronoi by Visual Capitalistによる地域別可視化半導体生産量データ(1990-2032F)によれば、中国の生産量シェアは1990年では0%であったのに、2020年では米国を抜いて15%になっている。2025年には予測値であるものの、米国を遥かに抜いて24%に跳ね上がっている。2025年の予測値は、複数のデータで概ね一致しているので、信頼できる数値として扱う。それを含めた米中の推移を図表1にプロットしてみた。
図表1:世界の半導体生産における米中シェアの推移

NISTとVoronoiのデータを基に、グラフは筆者が作成
中国の世界シェアは2013年以降に急増し、明らかに習近平政権のハイテク国家戦略「中国製造2025」の成果が発揮されていることがうかがわれる。
米国の世界シェアがひたすら下降していった背景には、米国の製造業そのものが長い時間をかけて衰退し、エンジニアもいなくなっていった大きな社会背景がある。その一方で米国は強い米ドルを中心として金融業ばかりに力を入れてきた。その証拠を図表2および図表3に示す。
図表2:米製造業と金融業が米GDPに貢献した割合の推移

アメリカ商務省経済分析局のデータを基にグラフは筆者が作成
図表3:米製造業・金融部門等の雇用者数の規模推移

アメリカ労働統計局のデータを基にグラフは筆者が作成
図表2や図表3が示す巨大な社会構造が、図表1の惨状を招いているのが明らかだろう。トランプ大統領はアジア諸国が「産業を盗んだ」としているが、基本的に犯人は米国自身であることを認識すべきではないだろうか。この根本原因を無視して、「半導体に100%の関税」をかけたり、海外半導体企業の誘致などという、他国に犠牲を強いる、小手先の戦略では、米国半導体が真に復活できるとは思えない。
◆米国の半導体輸入先シェア マレーシアやベトナムを迂回した中国製半導体
ならば現在、米国は半導体をどの国から輸入しているのだろうか?
米国で使用されている輸入品の関税率を計算するための分類システムにHTSコード(Harmonized Tariff Schedule)というのがある。USITC(United States International Trade Commission=アメリカ国際貿易委員会)のデータの中から関連HTSコードを抜き出して、米国の半導体の輸入先シェア2024を作成し、それを図表4として示す。関連HTSコードは、たとえば【HTSコード8541+8542】の合計(たとえば8541は半導体デバイス、8542は集積回路など)などである。
図表4:米国の半導体輸入先国のシェア

USITCのデータを基に、グラフは筆者作成
台湾にはTSMCがあるので別格とすれば、なんと、マレーシアからの輸入が一番多い。マレーシアは特に半導体生産で秀でているわけではないので奇妙だと思って調べてみたところ、案の定、中国製半導体の迂回をしていることがわかった。
2023年12月17日(最終更新は12月19日)、ロイターは<独占記事:中国企業はハイエンドチップの組み立てをマレーシアに期待していると関係筋が>という見出しで、少なからぬ中国の半導体設計企業が、最後のパッケージの段階をマレーシアに委託していると報道した。中国の半導体産業に対する制裁を米国が拡大するリスクを回避するため、ますます多くの中国の半導体設計企業がマレーシア企業と協力して、一部のハイエンドチップを現地でパッケージ化しているとのことだ。マレーシアにおける生産工程は組み立てのみであり、米国の規制に違反することはないとマレーシア側は主張している。
図表4で台湾を別とすれば、次に多いのがベトナムからだ。11%もの半導体をベトナムから輸入しないと米国の半導体業界が立ち行かないというのは感覚的にピンとこない。そこで、中国の半導体の輸出先を調べてみたところ、案の定、ベトナムに多く輸出していることが分かった。それを図表5に示す。
図表5:中国の半導体輸出先国のシェア

中国税関総署のデータに基づいて、グラフは筆者が作成
つまり「香港経由」で世界各国に渡り、ベトナムやマレーシア経由で米国に渡る。だから図表4にあるように、米国の半導体輸入先が「マレーシア」とか「ベトナム」といった摩訶不思議な現象が起きているのである。
それにしても、あの米国が中国から半導体を輸入――?
なんとも理解できない現象だ。
しかし、4月13日の論考<米軍武器の部品は中国製品! トランプ急遽その部品の関税免除>や4月16日の論考<中国最強カードを切る! 「米軍武器製造用」レアアース凍結から見えるトランプ関税の神髄>などをご覧いただければ、米軍の武器は中国製部品や中国から輸入されるレアアースなしでは製造できないことが明確になっている。
但し、そこで必要とされているのは主として7ナノ以下のようなレガシー半導体ではあるが、それでも「製造業」そのものがほぼ崩壊しているような米国では、レガシー半導体でも、中国から輸入しなければ米軍武器が製造できないのが現状だ。
とは言っても、たとえばエヌビディアのAI半導体のような最先端半導体は、逆に中国が米国から輸入しなければならなかった。
◆トランプの対中制裁の間に中国製AI半導体が中国市場を席捲し始めた
ところが、トランプ2.0になって、それまで何とか許されていたエヌビディアのAI半導体H20(エヌビディアが米国の輸出管理政策に対応する形で開発した中国市場向けの半導体チップ)までが禁輸の対象になってしまった。これに対してエヌビディアのジェンスン・ファンCEOの猛烈な反対があったり、米軍武器が中国製部品やレアアースなしでは製造できない現実にぶつかり、米中関税交渉の中で中国のレアアース輸出規制などとの交換条件のような形で米側が譲歩し、H20は輸出再開の許可を得るに至った。
しかし、中国市場はそのわずか3ヵ月ほどの間に中国製AI半導体を購入する方向に動いてしまったのである。そのことが中国のIT分野に強いメディア「36Kr」に書いてある。拙著『米中新産業WAR』でも触れたMoore Threads (ムーア・スレッド)の「MTT S80」やファーウェイの「Ascend(アセンド、昇騰) 910C」をはじめ、百度系の昆崙芯片科技(Kunlunxin)の「P800」あるいは中国科学院系の寒武紀科技(カンブリコン)の「思元590」などが中国市場で人気を博すようになったのだ。
拙著執筆時点では、こういった中国製AI半導体が生まれつつあり、エヌビディアのAI半導体に近づくには「あと一歩ながら、まだ遠い」と書いたのだが、それがトランプ2.0におけるH20の禁輸によって、逆に一気に成長したのだから皮肉なものである。
その背景にはAIスタートアップ企業DeepSeek(ディープシーク)の誕生もある。中国からOpenAIを凌駕するような企業が生まれ、大規模言語モデルにおいて、中国がアメリカと同じラインに並んだことに、中国市場は自信と誇りを持ち、それまで「H20には到底及ばない」と見ていた中国製AI半導体が堂々と「H20の代替品」として人気を博すようになった。
一般にAIは長い訓練学習期間が必要で、そのために何万台ものGPU(Graphics Processing Unit=画像処理装置)を並列しなければならず、その上で一般利用者が使うときに推理して回答を出す。DeepSeekの場合はさまざまな技術によって訓練・推理にかかるコストを大幅に削減しているだけでなく、「推理モデル」も開発している。
H20に慣れていて、H20の方が使い勝手がいいと思っていた市場も、DeepSeekの誕生とトランプ2.0の禁輸により、「中国製AI半導体」へと一気に向かっていったということだ。
それは「わずか3ヵ月間」という、一瞬の出来事だった。
その結果、対米輸出に関係している中国の半導体企業は、今では買い手のニーズを満たすことができないほど忙しく、トランプの「半導体に100%の関税」などにかまっていられない状況に至ったのだ。
前掲の36Krは「5月20日に台湾で開催されたコンピューター関連機器の展示会(Computex 2025)で、エヌビディアのフアンCEOは、中国のAIチップ市場におけるエヌビディアのシェアが2022年の95%から、米国の輸出規制の影響を受けて2025年には約50%まで低下したと明らかにした」と書いている。
7月31日に、中国の国家インテ―ネット情報弁公室は、<H20にバックドアが設置されていることに関してエヌビディアの担当者を呼び出した>ことが報道されたことなどもあり、今後H20の中国における市場は衰退していくだろうことが考えられる。
加えて、今年7 月 29日、ウォールストリート・ジャーナルは<中国は米国とのAI戦争にどう備えているか>(有料)という見出しで「米国政府が中国の進歩を阻止しようとしている中、中国政府は米国の技術に依存しないAIの構築に注力している」と前置きして、「モルガン・スタンレーは、2027年までに中国のAI半導体の82%が中国製になり、2024年の34%から増加すると予測している」と書いている。これは即ち、習近平政権が2015年に発布したハイテク国家戦略「中国製造2025」が完遂したことを意味する。
トランプの「半導体に100%の関税」で困るのは、何としても中国の半導体製品を必要としている米軍武器製造関連者や自動車製造関連者かもしれない。米国にはない製品を中国が持っているので、100%の関税がかけられても購入しようとするからである。
もっと困惑しているのは台湾ではないだろうか。
図表4にあるように、米国は半導体の19%を台湾から輸入している。TSMCなどは、膨大な資金をかけて米国に工場を建設しているが、それでもその部分には関税がかからなくても、台湾から輸出される残りのTSMC製半導体には100%の関税をかけるというのだから、たまったものではないだろうと推測される。
図表4を見ると、日本からの輸入は3%と少ないものの、日本政府は覚悟あるいは認識しているのだろうか。
米中の関税交渉はまだ続いているが、少なくとも「半導体100%関税」による影響は、中国はほぼ受けないことが今般の考察で見えてきた。トランプのことだから、次に何が起きるか不確定要素はあるものの、今のところトランプの関税戦略は、残念ながら、中国に有利に働いている。
この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。
カテゴリー
最近の投稿
- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ
- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?
- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!
- A January to Remember
- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma
- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」
- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?
- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く
- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く
- 2025年は転換点だったのか?