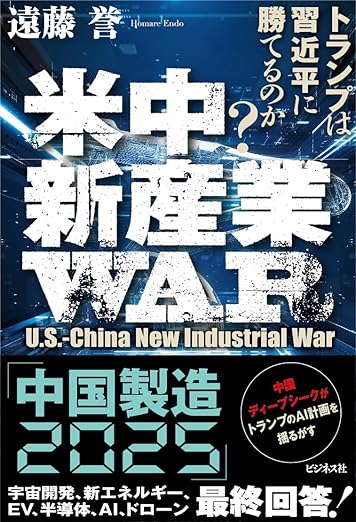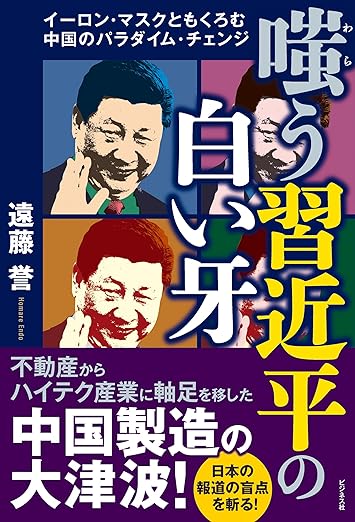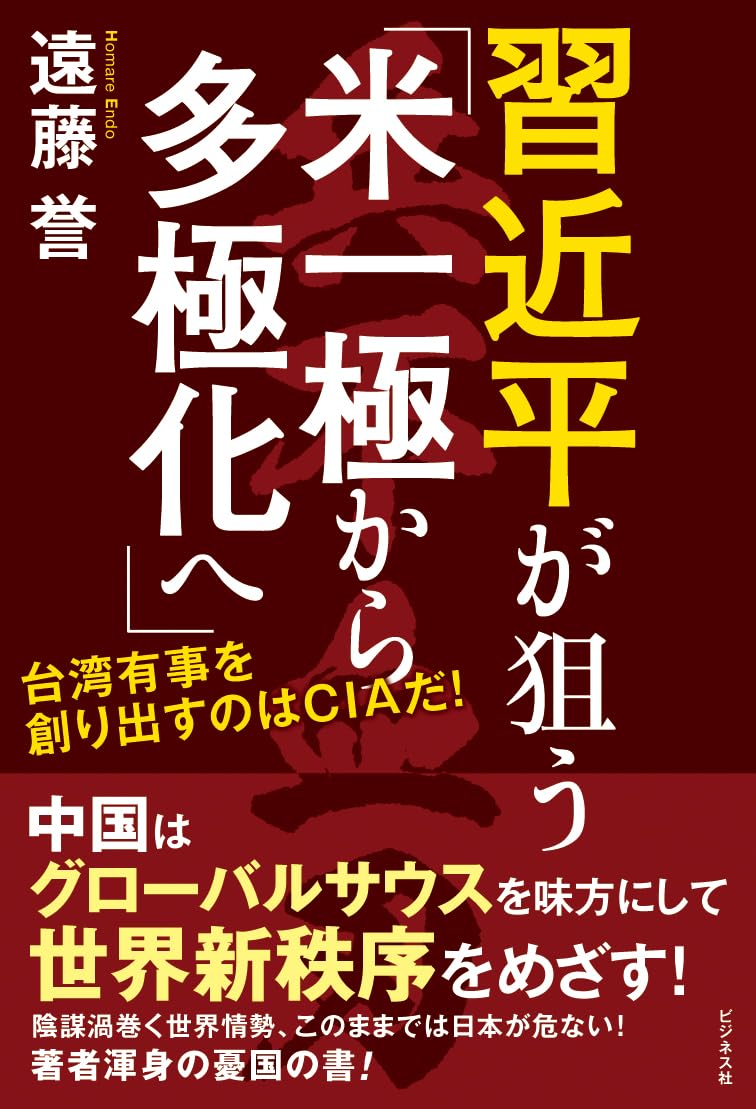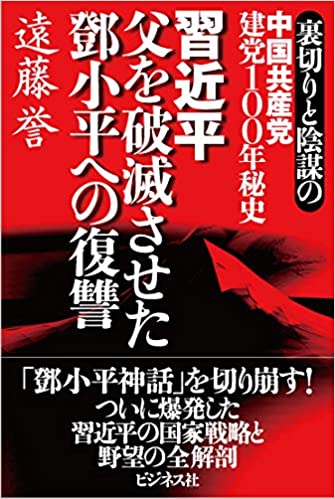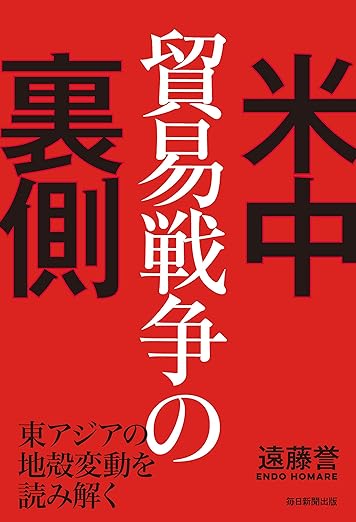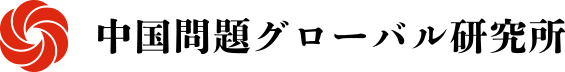2月24日午後1時、CCTVの画面に大きく映し出されたウクライナ大統領が悲痛な声で叫んでいた。バイデンは昨年12月7日のプーチンとの会談後「戦争になっても米軍は派遣しない」と言っていたと解説委員が強調した。
ハッとした!
これだ――!
これだった。私はこの事実を十分に認識していなかったために、プーチンの軍事侵攻の分析を誤ったのだ。猛烈な悔恨に襲われた。加えて2月24日の夜になると、NATOも部隊派遣をしないと決定した。これではウクライナがあまりに哀れではないか。
言うまでもなく、プーチンの軍事侵攻は絶対に許されるものではない。
それを大前提とした上で、ウクライナで何が起きていたのか、原点に立ち戻って確認しなければならない。私にはその責任がある。
◆ウクライナのゼレンスキー大統領の悲痛な叫び
2月24日午後1時、中国共産党が管轄する中央テレビ局CCTVのお昼の国際ニュースを観ていた時だった。
画面いっぱいに大写しになったウクライナのゼレンスキー大統領が「ウクライナは如何なる安全保障聯盟(軍事同盟)にも入ってないのです。だからウクライナ人の命の代償を以て自分たちを守るしかないのです・・・」と叫んでいた。
ほとんど泣きそうな表情だった。
続けてキャスターが「アメリカはあれだけゼレンスキー大統領を焚きつけて国際世論を煽りながら、その責任は取らないのです」と説明しながら、サキ報道官の姿を大きく映し出した。

2月24日、CCTV4のお昼のニュースより
字幕には、
ホワイトハウス:アメリカは如何なる状況になろうとも決してウクライナに派兵しない
と書いてある。サキ報道官の英語も流れていた。
頭を殴られたような衝撃に打ちのめされた。
ああ、これだ!
分析のジグゾーパズルの中に、このひと欠片(かけら)が抜け落ちていたのだ。
だとすればプーチンがこのチャンスを逃すはずがないだろう。バイデンはプーチンに「さあ、どうぞ!自由に軍事侵攻してください」というサインを与えていたのと同じで、プーチンがウクライナに軍事侵攻しないはずがない。
そう言えば、たしかに日本のメディアでも<ウクライナ国境付近でロシア軍が兵力を増強して緊張が高まっている問題で、米国のバイデン大統領は8日、米軍をウクライナ国内に派遣してロシアの軍事侵攻を阻むことについて、「検討していない」と否定的な考えを示した>と報道していた。
しかしそこには<「それは他のNATO加盟国の行動次第だ」と述べ、状況によっては米軍が介入する余地を残した>とも書いてあった。だからまさか本気で派兵しないなどという選択をするはずがないと思ってしまったのだ。
◆アフガン米軍撤退後のバイデンの行動
昨年8月31日にバイデンはアフガニスタンからの米軍の撤退を終え、そのあまりに非人道的な撤退の仕方に全世界から囂々(ごうごう)たる批難を浴びた。アメリカに協力していたNATO諸国はバイデンのやり方に失望し、心はアメリカから離れていった。
「アメリカ・ファースト」のトランプから大統領のポストを奪うことに成功したバイデンは、「アメリカは戻ってきた」と国際社会に宣言していたが、その信頼は失墜し、支持率もいきなり暴落した。
そこで思いついたのは、バイデンが長年にわたって培ってきた地盤であるウクライナだったのだろう。バイデンはいきなり軸足をウクライナに移し、9月20日にはNATOを中心とした15ヵ国6000人の多国籍軍によるウクライナとの軍事演習を展開した。このウクライナとの演習は1996年から始まっているが、開始以来、最大規模の演習だったと報道されている。
10月23日になると、バイデンはウクライナに180基の対戦車ミサイルシステム(シャベリン)を配備した。
このミサイルはオバマ政権のときに副大統領だったバイデンが、ロシアのクリミア併合を受けてウクライナに提供しようと提案したものだ。しかしオバマはそれを一言の下に却下した。「そのようなことをしたらプーチンを刺激して、プーチンがさらに攻撃的になる」というのが却下した理由だった。
このミサイルをウクライナに提供したらプーチンが攻撃的になる――!
オバマのこの言葉は、きっとバイデンに良いヒントを与えてくれたにちがいない。
案の定、バイデンがウクライナに対戦車ミサイルを配備したのを知ると、プーチンは直ちに「NATOはデッドラインを超えるな!」と反応し、10月末から11月初旬にかけて、ウクライナとの国境周辺に10万人ほどのロシア軍を集めてウクライナを囲む陣地配置に動いた(ウクライナのゼレンスキー大統領の発表)。
アメリカ同様、通常の軍事訓練だというのがプーチンの言い分だった。
こうした上で、バイデンは何としてもプーチンとの首脳会談を開きたいと申し出て、2021年12月7日の会談直後に「ウクライナで戦いが起きても、米軍派遣は行わない」と世界に向けて発表したのである。
◆ウクライナ憲法に「NATO加盟」を努力目標に入れさせたのはバイデン
バイデンは副大統領の期間(2009年1月20日~2017年1月20日)に、6回もウクライナを訪問している。
訪問するたびに息子のハンター・バイデンを伴い、ハンター・バイデンは2014年4月にウクライナ最大手の天然ガス会社ブリスマ・ホールディングスの取締役に就任した。この詳細は多くのウェブサイトに書いてあるが、最も参考になるのは拓殖大学海外事情研究所の名越健郎教授がまとめた<「次男は月収500万円」バイデン父子がウクライナから破格報酬を引き出せたワケ安倍政権の対ロシア外交を妨害も>だ。これは実によくまとめてあるので、是非とも一読をお勧めしたい。
しかし、これらの情報のどこにも書いてないのが、バイデンが副大統領として活躍している間に、意のままに動かせたポロシェンコ大統領(2014年6月7日~2019年5月20日)を操って、ウクライナ憲法に「NATO加盟」を努力義務とすることを入れさせたことだ。
私はむしろ、この事実に注目したい。その経緯の概略を示すと以下のようになる。
- 2017年6月8日、「NATO加盟を優先事項にする」という法律を制定させた。
- 2018年9月20日、「NATOとEU加盟をウクライナ首相の努力目標とする」旨の憲法改正法案を憲法裁判所に提出した。
- 2018年11月22日に憲法裁判所から改正法案に関する許可が出て。
- 2019年2月7日に、ウクライナ憲法116条に「NATOとEUに加盟する努力目標を実施する義務がウクライナ首相にある」という趣旨の条文が追加された。
(後半の3項目に関してはこちらを参照。)
プーチンのウクライナに関する警戒は、こうして強まっていったのである。
◆ハンター・バイデンのスキャンダルを訴追する検事総長を解任させた
なぜ、この憲法改正にバイデンが関係しているかを証拠づける、恐るべきスキャンダルがウクライナで進行していた。
バイデン副大統領の息子ハンター・バイデンが取締役を務めるブリスマ・ホールディングスは脱税など多くの不正疑惑を抱いたウクライナの検察当局の捜査対象となっていた。
しかし2015年、バイデンはポロシェンコに対して、同社を捜査していたショーキン検事総長の解任を要求。バイデンはポロシェンコに「解任しないなら、ウクライナへの10億ドルの融資を撤回するぞ!」と迫って脅迫し、検事総長解任に成功した。その結果融資は実行された。
このことは検事総長が、解任されたあとにメディアに告発したと名越教授は書いている。
ウクライナの検事総長を解任する犯罪的行為を操れる力まで持っていたバイデンは、ウクライナに憲法改正を迫ることなど、余裕でできたものと判断される。
今般、ウクライナを焚きつけて騒動を起こさせた理由の一つに「息子ハンター・バイデンのスキャンダルを揉み消す狙いがあった」という情報を複数の筋から得ている。トランプ元大統領は、ゼレンスキーに「バイデンが、息子のスキャンダルを揉み消すために不正を働いた証拠をつかんでほしいと」と依頼したことがあった。アメリカで中間選挙や大統領選挙になった時に、必ずトランプがバイデンの息子のスキャンダルを再び突っつき始めるので、それを掻き消すためにウクライナで成功を収めておかなければならないという逼迫した事情がバイデンにはあったというのが、その情報発信者たちの根拠である。その時が来ればトランプがきっと暴き出すにちがいないと待っているようだ。
筆者はシンクタンク中国問題グローバル研究所を運営していて、そこには複数のロシアの研究員がいるだけでなく、習近平を批判するようなシンクタンクに研究員として名前を出すことは(プーチンの怒りに触れるので)出来ないが、実情報告なら個人的に行ってもいいと言ってくれる研究者が何名もいる。
実は筑波大学には世界100ヶ国以上から外国人留学生が来ていて、一橋大学や千葉大学を含めて30年間以上にわたり留学生センターで相談業務に当たっていた筆者は、各国からの国費留学生の相談に乗ってあげていたので、世界各国には、すでに中堅以上の人物になっている「教え子」がネットワークを作ってくれている。
それらの情報によれば、「アメリカで中間選挙や大統領選挙になった時に、必ずトランプがバイデンの息子のスキャンダルを再び突っつき始めるので、それを掻き消すためにウクライナで成功を収めておかなければならないという逼迫した事情がバイデンにはあった。その時が来ればトランプが必ず暴き出す」とのこと。
この情報は早くから入手していたが、証拠がないだろうという批判を受ける可能性があり、日本がバイデンの表面の顔に完全に支配されてしまっている状況では、とても日本人読者に受け入れてもらえないだろうと懸念し、こんにちまで書かずに控えてきた。
しかしウクライナをここまで利用して翻弄させ、結果捨ててしまったバイデンの「非人道的な」なやり方に憤りを禁じ得ず、ここに内幕を書いた次第だ。
◆NATOもウクライナに応援部隊を派遣しない
筆者に、思い切って正直に書こうと決意させた動機の一つには、2月24日夜21:22に共同通信社が「部隊派遣しないとNATO事務総長」というニュースを配信したこともある。
それによれば「NATOのストルテンベルグ事務総長は24日の記者会見で、東欧での部隊増強の方針を示す一方、ウクライナには部隊を派遣しないと述べた」とのこと。
バイデンは2021年12月8日の記者会見で「他のNATO加盟国の行動次第だ」と言っていた。
NATO事務総長の発表は、バイデンに「NATOが派遣しないと決めたのだから、仕方がない」という弁明を与え、米軍がウクライナへ派兵しないというのは、これで決定的となっただろう。
あまりに残酷ではないか――!
ウクライナをここまで焚きつけて血を流させ、自分は一滴の血も流さずにアメリカの液化天然ガス(LNG)の欧州への輸出を爆発的に加速させることには成功した。
おまけにアフガン撤退によって離れていったNATOの「結束」を取り戻すことにもバイデンは今のところ成功している。
この事実を直視しないで、日本はこのまま「バイデンの外交工作に染まったまま」突進していいのだろうか。
このような「核を持たない国を焚きつけて利用し、使い捨てる」というアメリカのやり方から、日本は何も学ばなくていいのだろうか。
物心ついたときにソ連兵の家屋侵入に怯えマンドリンの矛先に震えた経験を持つ筆者は、プーチンのやり方を見て、アメリカの日本への原爆投下に慌てて第二次世界大戦に参戦し素早く長春になだれ込んできたソ連兵を思い起こした。
ソ連はいつも、こういう卑劣な急襲を行う。そして日本の北方四島を掠め取っていった。その伝統はロシアになっても変わっていない。
一方では「核を持つ国アメリカ」のやり方は、日本の尖閣諸島防衛に関しても、ウクライナを利用し捨てたのと同じことをするのではないかと反射的に警戒心を抱いた。なぜならバイデンはウクライナに米軍を派遣しない理由を「核を持っているから」と弁明したが、それなら「中国も核を持っている」ではないか。
「米露」が核を持っている国同士であるなら、「米中」も核を持っている国同士だ。だから万一中国が尖閣諸島を武力攻撃しても、「米軍は参戦しない」という論理になる。
自国を守る軍事力を持たないことの悲劇、核を捨てたウクライナの屈辱と悲痛な悲鳴は、日本でも起こり得るシミュレーションとして覚悟しておかなければならないだろう。
そのことを日本の皆さんに理解して頂きたいという切なる思いから、自戒の念とともに綴った次第だ。真意をご理解くださることを切に祈りたい。
追記:ニクソンは大統領再選のために米中国交樹立を謳い(1971.04.16)キッシンジャーに忍者外交をさせて(1971.07.09)、中華人民共和国(中国)を国連に加盟させ中華民国(台湾)を国連から追い出した(1971.10.25)。それがこんにちの「言論弾圧を許す」中国の巨大化を生んだ。大統領再選のためならアメリカは何でもする。そのアメリカに追随する日本は、天安門事件で対中経済封鎖を解除させることに奔走し、モンスター中国を生んだ。その中国がいま日本に軍事的脅威を与えている。この大きな構図を見逃さないでほしい。結果は後になってわかる。
カテゴリー
最近の投稿
- Internationalizing the Renminbi
- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する
- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ
- 記憶に残る1月
- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機
- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ
- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?
- A January to Remember
- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma