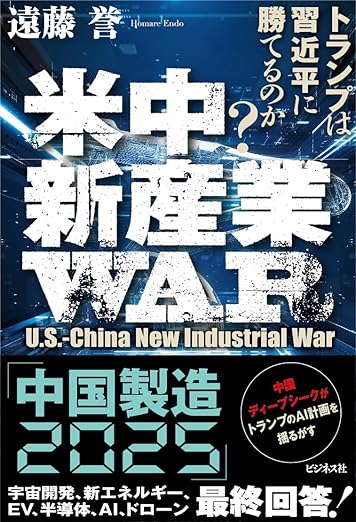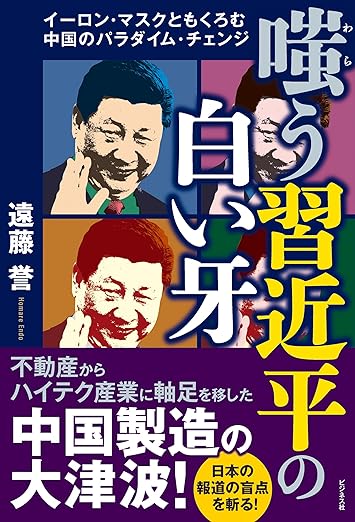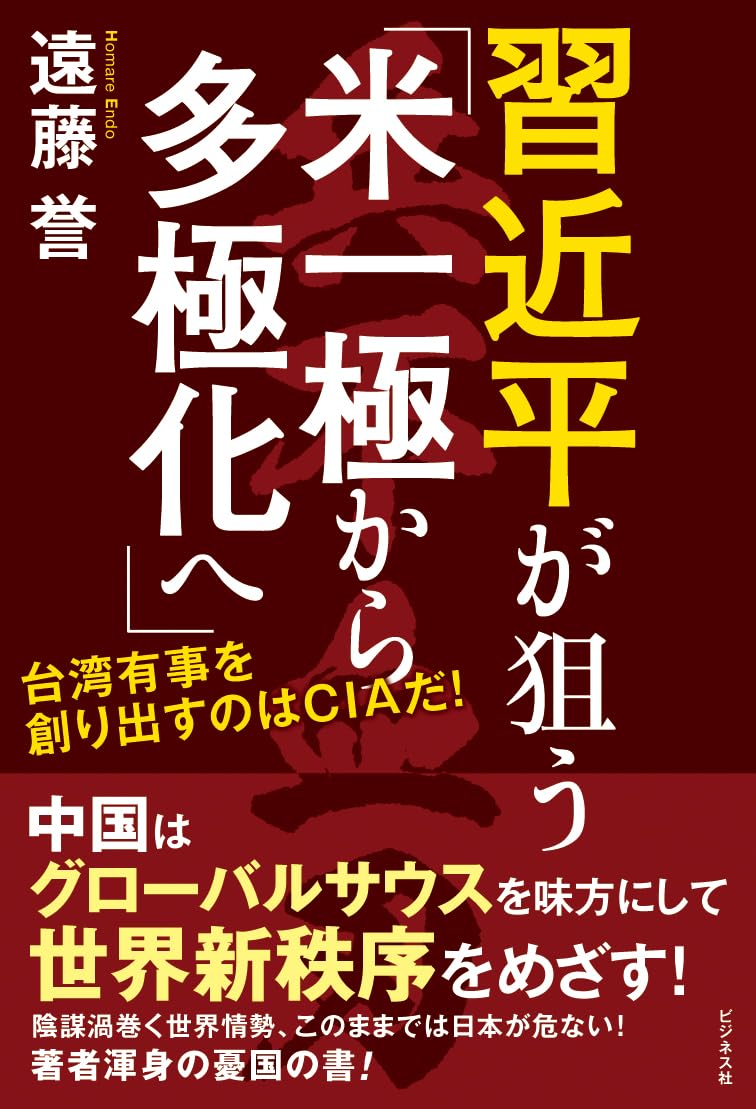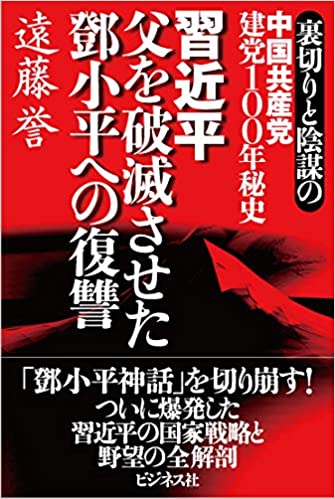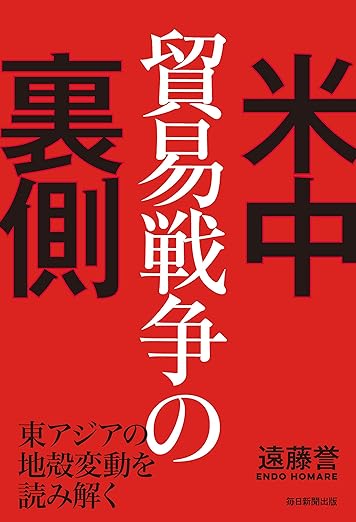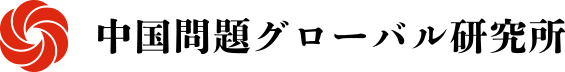中国共産党が誕生し革命戦争を通して中華人民共和国が建国されて以来、いま残っている国家リーダーになる器を持った者で、かつ革命の紅いDNAを引いている男は習近平以外にいない。彼の後に出てくるのは小粒でしかない。
◆紅いDNAを引く最後の男
1921年に中国共産党が誕生した。習近平の父・習仲勲(1913年~2002年)は陝西省富平県に生まれたが、建党後ほどなくして中国共産主義青年団(共青団)に入団し、陝西省で革命活動に参加し始めたが、1928年に学生運動に参加した際に投獄され、獄中で中国共産党員になっている。わずか15歳だった。
やがて釈放された習仲勲は、陝西省や甘粛省などの一帯に「陝甘辺ソビエト政府」を樹立するなどして革命根拠地(のちの西北革命根拠地)を築くのだが、その中に「延安」があった。
蒋介石率いる国民党軍に敗れた毛沢東率いる紅軍は、1934年10月、最後の中華ソビエト共和国の拠点であった江西省瑞金を放棄して、1万2500キロを徒歩で北西方向に向かった。これを「長征」という。
しかし中国全土に構築した革命根拠地はほとんど国民党軍に殲滅されて、唯一、習仲勲らが建設していた陝甘辺ソビエト政府だけが残っていた。
毛沢東一行が延安に到着したのは約1年後の1935年10月である。
もしあのとき、陝甘辺ソビエト政府という革命根拠地が残っていなかったら、毛沢東は長征の到着先を見つけることができず、共産党軍が国民党軍に勝利して中華人民共和国を建国することはできなかった。
したがって、中華人民共和国が誕生したのは、習仲勲等のお陰である。
だから毛沢東は習仲勲に感謝し、習仲勲をこの上なく可愛がった。
習仲勲を「諸葛孔明よりもすごい」と褒めたたえたことさえある。
鄧小平は、それが怖かった。人一倍野心に燃えていた鄧小平は、このままでは自分が毛沢東の後継者になるチャンスはなくなると計算し、さまざまな陰謀をめぐらして習仲勲を失脚させ、16年間も軟禁や獄中生活を送らせるところに陥れてしまったのである(その証拠は、『習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐』で示した)。
しかし、その息子・習近平は生き残り、最終的には江沢民が自分の駒として習近平を取り立てたために、今日のポジションがある。
いま習近平世代で、中国のトップリーダーになる器を持った人物を眺めたときに、「革命の紅い血」をストレートに引き継いでいる者は一人もいない。
日本のメディアや研究者あるいはチャイナ・ウォッチャーの中では、習近平が権力闘争のために反腐敗運動を展開し、李克強との間でもライバル意識を持って李克強に権力を渡すまいとしているといった類の分析をする人が数多く見られるが、その人たちは習近平が圧倒的に他と異なる「紅いDNA」を持った唯一の人物であることに気が付いていないのではないだろうか。
習近平は「紅いDNA」を持つ、中国最後の人物なのである。
習近平が引退した後に出てくる人物は、たとえ誰であっても、その意味では小粒で、習近平以上の「革命の正統性」を持った者は二度と現れない。
◆「江沢民‐朱鎔基」、「胡錦涛‐温家宝」、「習近平‐李克強」との比較
過去の指導者である「国家主席(&総書記)‐国務院総理(首相)」のペアで、「江沢民‐朱鎔基」と「胡錦涛‐温家宝」および「習近平‐李克強」を比較して、習近平の独裁欲の強さ、あるいは李克強の影の薄さを論じたメディアもあり、興味を引いた。ただ、この3組はあまりに状況が異なり、ちょうど良い例でもあるので、筆者なりの比較を試みてみよう。
江沢民の父親は日中戦争時代、日本の傀儡政権として南京に樹立された汪兆銘政権の官吏で、中国語で言うならば「漢奸(ハンジェン)」、すなわち売国奴である。その出自を隠そうと、1995年から激しい反日教育を始めたくらいで、「紅いDNA」の反対側の人間だ。能力もないのに(だからこそ気に入られて)鄧小平の「鶴の一声」で中共中央総書記になり(1989年)、1993年に初めて国家主席になるという尋常でない道を歩んでいる。本来ならそのときの国務院総理だった李鵬に代わって、実力の高い朱鎔基が国務院総理になるはずだったが、朱鎔基の実力を同じ上海にいたときに知っていた江沢民は、朱鎔基が国務院総理になるのを嫌った。そのため1998年になってようやく、朱鎔基は国務院総理になった。しかし江沢民は依然として朱鎔基に対してはライバル心むき出しで、常に朱鎔基に後れを取るものだから、喧嘩ばかりしていた。
胡錦涛と温家宝は非常に仲が良かったが、しかし胡錦涛には「紅いDNA」はない。胡錦涛の祖父は商売人で、父親は小学校の教員。生活苦からお茶の販売もしていた。やはり商売人だ。共産党とは無縁の家庭で育っている。清華大学に入学してから共産党と接するようになり入党した、よくある共産党員のパターンである。
温家宝も似たようなもので、天津の郊外にあった教員の家庭で育っている。胡錦涛と温家宝には共通する先輩がおり、二人とも、1977年から81年まで甘粛省の書記だった宋平によって抜擢されている。胡錦涛が共青団で幹部プログラムに参加したのは、宋平の推薦があったからだ。温家宝も宋平のお陰で中央入りしているので、胡錦涛と温家宝は「親が教員だった」という共通点と宋平の存在により「仲良し」だったのである。
誰一人、「紅いDNA」を持っていない。
しかし習近平は違う、誰よりもストレートに建党と建国の血筋を持って生れ出てきており、この「革命の紅い血」は、中国においては絶対的なのである。
李克強はそもそも「がり勉さん」で、権勢欲はなく、カリスマ性も特にない。彼自身、国務院総理であることに満足しているように見受けられるし、実務能力は高いので国務院総理に似合っている。父親は1929年に安徽省の田舎で共産党に入党し小学校の教員になったり、兵士として戦ったりしたこともあるが、あくまでも地方の田舎での活動に終始し、中央と関わったことはない。教育にはことのほか熱心で、いかにも李克強の人間性が育て上げられた環境らしい。
ただ、習近平の「紅いDNA」と比較したら、比較の対象ではないことを李克強自身も分かっているだろう。
こうして、過去三代の指導者のペアと比較しても、習近平だけは際立って「紅い革命の血」が濃いことがわかる。ましてや今現在の周辺(少なくとも現在中共中央政治局委員までは上がってきている者)を見渡しても、あるいは一つ下の世代の候補者(中共中央委員会委員)を見渡しても、建党・建国以来の血筋を引く者は一人もいない。
◆三期目を狙う習近平
だからと言って憲法を改正してまで三期目を狙うのか、ということには抵抗を持つ党員もいないではないだろう。
しかし中国の経済も軍事力も圧倒的に強くなり、アメリカが脅威を感じて、あの手この手で中国を潰しにかかってきているときに、党員も一般人民も、「経済と軍事を強くしてくれたのだから」と習近平を肯定する傾向にある。
もちろん経済にはさまざまな問題を抱えてはいるものの、大国アメリカと対等に渡り合える「存在感」は、この「紅いDNA」が強めているのは確かだ。党員ともなれば、中国共産党がどこから立ち上がってきたのか、中華人民共和国が如何にして建国されたのかを思うとき、「紅い革命の血筋」は絶対的だ。
反腐敗運動により軍に巣食う腐敗の巣窟を除去し、2015年12月末日に軍事大改革を成し遂げた上で、第19回党大会で「習近平新時代の特色ある中国社会主義思想」を党規約に書き込んで翌年2018年3月に国家主席任期に関する制限を撤廃した。
もっとも、この制限、かつてはなかったもので、果たしてこれが「党内民主」という性格から来たものか否かは、実はそこには複雑な背景がある。
◆鄧小平ほど独裁的だった人は中国建国以来いない
習近平が「独裁的である」という批判は、世界中から受けているところだろう。
筆者自身も習近平をかつて「紅い皇帝」と位置付けて本を書いたことがある。その時にはまだ勉強が不十分で、まさか習近平の父・習仲勲が、鄧小平の陰謀によって失脚させられたのだということを思いもしていなかったし、知らなかった。
しかしこのたび、『習近平父を破滅させた鄧小平への復讐』を書くに当たり、徹底して、これでもか、これでもかと追跡に追跡を重ねた結果、本当に鄧小平がさまざまな国家リーダーとなり得る人を倒してきたことを実感するに至った。
鄧小平がどれだけ多くの国家リーダーあるいはリーダーとなり得る人物を倒し、かつ自分が推薦して就任させておきながら、気に入らないと失脚させるということを繰り返してきたかを以下に列挙してみよう。
- 1954年:毛沢東が後継者に考えていた高崗(西北革命根拠地)を自殺に追い込んだ。
- 1962年:習仲勲を冤罪により失脚させた(16年間、軟禁・投獄・監視)。
- 1980年9月:華国鋒を国務院総理辞任へと追い込む。
- 1981年6月:華国鋒(中共中央主席、軍事委員会主席辞任)を失脚に追い込む
- 1981年6月:自分のお気に入りの胡耀邦を中共中央主席に就任させる。
(但し、1982年9月で中央主席制度を廃止し中共中央総書記に。) - 1986年:胡耀邦(中共中央総書記)を失脚に追い込み、趙紫陽を後任にした。
- 1989年:趙紫陽(中共中央総書記)を失脚に追い込んだ。
- 1989年:江沢民を一存で中共中央総書記・中央軍事委員会主席に指名。
- 2001年:胡錦涛を隔代指導者に、鄧小平の一存で決定した。
ここまで国家のトップを自分一人の意思で失脚させたり指名したりした人は、建国後の中国には存在しない。毛沢東でさえ、たった一人の国家主席(劉少奇)を失脚させるために、わざわざ文化大革命を起こさないと、一存で失脚させる力は持っていなかったし、そうしなかった。
その鄧小平が一存で決めた「国家主席の任期」を撤廃した習近平の「独裁度」は、遠く鄧小平に及ばない。
軟禁された趙紫陽は、テープに回顧録を録音し、それがのちに出版されたが、その中で趙紫陽は「鄧小平の声は神の声だった。すべては彼の一声で決まった」と語っている。
集団指導体制自体は鄧小平が決めたものではなく、毛沢東時代からあった。
国家主席に関する任期を区切ったのは鄧小平だが、習近平が撤廃したのは、このルールだけだ。
◆アメリカに潰されない国を求めて
中国はもともと、こういう国なのである。
それでもアメリカと対等に対峙できるリーダーを中国共産党員も中国人民も求めている。「紅いDNA」を持つ最後の男は、アメリカを凌駕するところまで粘るつもりではないだろうか。
岸田内閣はゆめゆめ「紅いDNA」の夢の実現に手を貸すようなことをしてはならない。日中国交正常化50周年記念を口実に、岸田内閣は何をするかわからない。今から警鐘を鳴らしておきたい。
カテゴリー
最近の投稿
- Old Wine in a New Bottle? When Economic Integration Meets Security Alignment: Rethinking China’s Taiwan Policy in the “15th Five-Year Plan”
- イラン「ホルムズ海峡通行、中露には許可」
- なぜ全人代で李強首相は「覇権主義と強権政治に断固反対」を読み飛ばしたのか?
- From Energy to Strategic Nodes: Rethinking China’s Geopolitical Space in an Era of Geoeconomic Competition
- イラン爆撃により中国はダメージを受けるのか?
- Internationalizing the Renminbi
- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する
- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ
- 記憶に残る1月