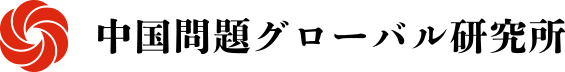G7は本来6月に開催されることになっていたが、コロナの感染拡大が続くので、ビデオ会議に変更されていた。しかしトランプがどうしても直接集まって開きたいと主張した。それに対してメルケルが参加を拒否したので、結局のところ9月まで延期されることとなった。
トランプ氏は当初、自ら所有するゴルフ・リゾートでの開催を考えていたが、その後、場所はキャンプデービッドかホワイトハウスの開催に変更されるなどごたごたが続いた。直接集まる会議にしたいというトランプ氏の欲求も、対話を真に強化したいという意欲からではなく、米国の経済活動が再開しすべてが正常に戻ったことをアピールする政治的な得点稼ぎを狙ったものとみられている。
しかし、トランプ氏にはこのような欠点が多数あっても、他の人間が言わないことを言う覚悟があり、実際にそうした発言することによって問題の核心に切り込んでいく。次の段階を考えたり、意味のある政策を立案したりすることは全くしていないが、その率直なスタイルは時としてもっともらしく響くことがある。
G7サミットの準備を進める中でトランプ氏はこう述べた。
「G7は世界の動きを適切に代表しているとは思えない。とても時代遅れの国家グループだ。」
2つ目の文はともかく、最初の文は確かに正しい。そこでトランプ氏は、インド、ブラジル、ロシア、韓国、オーストラリアの5カ国に招待を広げた。首脳会議がいつ開催されるのか、最終的に誰が出席するのかはまだ明らではないが、左の表を見ればこれらの国々が招待された理由がよく分かる。この表は、昨秋のIMFデータに基づく名目国内総生産(GDP)の規模を示している。パンデミック以降、これらすべて国の名目GDPは大幅に縮小している。
| 順位 | 国 | 名目GDP、兆米ドル | G7 メンバー | G11/12 に招待? |
| 1 | 米国 | 21.44 | Yes | |
| 2 | 中国 | 14.14 | ||
| 3 | 日本 | 5.15 | Yes | |
| 4 | ドイツ | 3.86 | Yes | |
| 5 | インド | 2.94 | Yes | |
| 6 | 英国 | 2.83 | Yes | |
| 7 | フランス | 2.71 | Yes | |
| 8 | イタリア | 1.99 | Yes | |
| 9 | ブラジル | 1.85 | Yes | |
| 10 | カナダ | 1.73 | Yes | |
| 11 | ロシア | 1.64 | Yes | |
| 12 | 韓国 | 1.63 | Yes | |
| 13 | スペイン | 1.4 | ||
| 14 | オーストラリア | 1.38 | Yes |
元々のG7は、もちろん日本も参加しているが、北大西洋地域への集中が明白だ。過去数十年間にアジアやラテン・アメリカで起きていることが反映されていない。インドとブラジルはともにカナダより経済規模が大きいので、招待は妥当に思える。韓国の参加は、GDPだけでなくアジアの発展を確かに反映している。韓国は近代的な第一世界の経済国というだけでない。パンデミックに卓越した対応をみせ、また今や、テレビドラマ、映画、ポップミュージックが世界のファンを引き付け賞も獲得するなど、そのソフトパワーを世界で競っている。
とはいえ、トランプ氏の招待が全面的に支持されているわけでもない。トランプ氏の一方的なG7再編の動きに対して欧州のメンバーは反発し、特にロシアの招待に反対している。2014年にロシアがクリミアに侵攻して以来、欧州連合(EU)と米国はロシアに制裁を科し、世界の政治舞台でロシアとは距離を置いたが、トランプ氏はロシアのウラジーミル・プーチン大統領を個人的に称賛し、ロシアとの関係を継続している。これが、EUのみならず、米国でもより広範な政治・外交分野の人々を不安にさせているのは確かだ。
欧州には、トランプ氏に対して反射的とも言える嫌悪感を持つ人々がいる。彼らは、無知と傲慢が入り混じったトランプ氏を我慢ならないと思っていて、何か別のことをしていればいいと望んでいる。この根本的な嫌悪感があるために、トランプ氏の提案は何であっても頭から拒絶する。また世界をより適切に代表するようグループを拡大するのは理にかなっているかもしれないが、それならば、なぜこれらの国だけにとどめるのか。イスラム世界はどの国が代表するのか。インドは、インドネシアとパキスタンに次いでムスリム人口が世界で3番目に多いかもしれないが、インドがイスラム世界の関心を適切に語れるとは誰も思わないだろう。中南米を代表する国も一つもないし、明白な欠落はアフリカの国がまったく言及されていないことである。アフリカ最大の経済国であるナイジェリアは、世界経済のトップ20にさえ入っていない。
もちろん、より多くの国が参加するG20や、世界銀行、アフリカ連合、ASEANのような国際機関がすでに存在しており、そこには、アメリカ大陸、アフリカ、アジアからより広範な参加がある。国際機関はともかく、G20はその規模からみて大き過ぎてかつ多様化し過ぎているため、意味のある影響を与えることができない。こうしたグループの多くは、すでにほとんど機能していないおしゃべりの場とみなされており、加盟国を増やすことはそうした見方をさらに強めるだけだ。
グループの拡大の動きは、「反中国フォーラム」になるので非現実的だとはみなされなかった。中国は一定の尺度でみれば世界2位の経済大国であり、経済成長率を誇張したり、新型コロナウイルス感染症の拡大で急減速したりしても、その現実は変わらないだろう。中国を抜きにしてこのような大国の世界的集合体を形成することは、それ自体が中国に対する事実上の挑戦である。ロシアは、そのような反中同盟に参加することには関心がないと明言しているため、トランプ氏のG12構想はうまくいってもG11ににとどまる。
しかし、ロシアだけでなく、これらの国すべてとは言わないまでも、ほとんどの国は中国を敵に回したいとは思っていない。中国および中国企業に対するトランプ氏主導の「聖戦」への参加を望んでいないのは明らかだ。もっとも、提案されているG12のメンバーのほとんどの国が中国との問題を抱えている。リストを順に見れば分かる。米国と中国の問題は説明の必要はない。日本と中国は何十年も前から緊張が続いている。ドイツは、特に中国によるドイツのハイテク・メーカーの買収で浮き彫りになったように、中国との間の非常に不平等な経済状況に次第に目覚めてきた。インドの場合、ヒマラヤでの激しい白兵戦で双方に数十人の死者が出たことで、改善しつつあった中国との関係は完全に頓挫した。英国はようやく、中国との関係の「黄金時代」はそれほどのものではなく、現在の関わり方を再考する必要があることを理解した。カナダで孟晩舟氏が逮捕、拘束された際、中国は2人のカナダ人を人質に取り、双方の拘束者を交換しようという厚かましい提案をして、カナダや自国の法律をないがしろにしていることを示した。ロシアと韓国にとっては中国との二国間貿易が重要であるが、巨大な隣国への警戒心を間違いなく持ち続けている。オーストラリアは、新型コロナウイルス感染症の流行拡大に関する透明性と情報開示を中国に求めており、中国は対抗してオーストラリアの輸出品に狙いを定めている。つまるところ、このグループはすでに中国と対立しているのだ。本来なら理想的な反中国グループに見えるだろう。
しかし、トランプ大統領の唐突な呼び掛けを別として、これらの国はいずれも中国との完全な分離を望んではいない。すべての国が中国との貿易や投資の関係を通じて何らかの形で利益を得ており、その継続を望んでいる。彼らがもはや受け入られないと考えているのは、中国が過去20年間続けてきた貿易ルールの乱用と歪曲、そして保護主義的措置である。中国が南シナ海で近隣諸国をいじめ、法的権利のない島を軍事化している中で、彼らはもはや黙ってはいられないだろう。中国は、自らの行動に対するあらゆる批判を、二国間関係全体を危険にさらす中国国民への侮辱と決め付けることを狙っており、彼らはもはやそうした中国による国内政治への干渉を受け入れないだろう。あることを約束しても別のことを行う中国をもはや受け入れないだろう。中国との首脳会議をこのほどビデオ通話形式で開催したEUは、中国に対し、香港問題から貿易、市場の相互主義に関するものまで一連の失策について警告した。これらの国々には共通の目的が多数あるが、欠けているのはリーダーシップと戦略であり、それを発揮できるのは米国だけだ。米国の経済的な影響力は他のすべての国を圧倒しており、多くの経済指標と開発指標において依然として中国をリードしている。
トランプ大統領の無知と傲慢さは確かに世界中の多くの人々をうんざりさせている。しかし結局のところは、トランプ氏が意味のある長期的戦略と関連政策の策定に完全に失敗したために、軽率にツイートされた行動方針に参加しようという他国の意欲が萎えているのだ。たとえそのような戦略が提案されたとしても、トランプ氏が政策を前進させるための集中力と規律を持つとは誰も信じていない。ジョン・ボルトン前大統領補佐官(国家安全保障問題担当)の著書で明らかになったことからも、またウクライナを巡る過去の調査からも、トランプ氏は国家としての必要性よりも、自分の問題を優先し、何が再選につながるのかを常に優先していることが明らかである。ボルトン氏によれば、トランプ氏は習近平国家主席に対し、農産物をもっと購入して米国の農業州での得票数を増やし再選を支援するよう実質的に要請したという。突然トランプ氏に切り捨てられる可能性があるのに、他のG12諸国がどうして彼にリーダーシップを期待できるだろうか。トランプ氏は、世論調査の数字が落ちていると考えたら、深夜のツイートで数週間にわたる交渉を白紙に戻すかもしれないのだ。
皮肉なことだが、もし米国が中国の政策と慣行を変えるため意味のある方策を望むのであれば、G7の拡大という形であるのかはともかく、そうした同じ考えの国々のグループを作ることがまさにできたはずである。中国の過剰な行動を押し戻すことは、短期的で簡単なプロセスだと考えてはならない。それは、単一の貿易協定だけで、あるいは単一の協定がいくらあったとしても、実現されることはなかった。そのためには協調した行動と手段が必要であり、一連の問題を横断的に調整しなければならない。
トランプ氏はG11やG12の首脳会議を試みてはいるが、失敗はほぼ確実だ。彼は、多くの個別の国に争いを仕掛けることで、あらゆる協調の可能性を自ら切り捨ててきた。EUは、自動車とデジタル・サービスを巡ってトランプ氏との貿易戦争に向かっている。日本と韓国に対してトランプ氏は既に貿易と関税に関心を寄せている。NATOに関する発言でドイツを怒らせ、カナダとの争いさえ辞さない。その怒りの矛先を免れているのはロシアだけだ。英国の離脱により、EUと英国の間で新たな貿易協定と「離婚調停」のための厳しい交渉が続き、英国とフランス、ドイツ、イタリア間の貿易関係の緊張は高まる一方である。要するに、このグループは中国に対する政策で協調する前に、互いに争うことが多過ぎるのだ。
トランプ大統領は、中国を巡る対話と相互関係に長年待ち望まれていた変化をもたらし重要な第一歩としたが、中国への対抗という点では本来の同盟国をすべて遠ざけてしまった。彼の大統領職における最初の目標、そしておそらく彼の唯一の大きな実績は減税だったが、中国への対応という点では、同盟関係を強化しさらに他にも広げることを計画すべきだった。その代わりにトランプ氏は、友人や同盟国を軽視して、「アメリカ・ファースト」ではなく「アメリカ・オンリー」の政策を推進してきた。
現在、世界的なリーダーシップは極めて重要である。パンデミックがもたらした保健医療の問題、それに伴う深刻な景気後退は、協調した政策行動によってのみ対処できる。G7はその政策の方向性を決める上で重要な役割を果たす。9月のサミットで前進できることが重要である。しかし、G12に関心を持つ国々にとってさえ、重要な変化は米国の政策からもたらされる必要がある。米国の政治や政府のシステムの中には、歴史的な同盟国と協力して、中国に対して有意義かつ効果的な政策を立案したいと熱心に考えている有能な人材が数多くいる。あらゆる分野のそうした優秀な人々が今度の機会を大切にしたいと考えているが、時間は浪費されている。中国が、世界の他の国々に対してより優れたアイデアや戦略を持っているわけではない。しかし、多くの主要国が互いに対立し、ビジョンとリーダーシップを示せない中で、中国は可能な限りその存在を拡大し続けるだろう。
カテゴリー
最近の投稿
- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する
- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ
- 記憶に残る1月
- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機
- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ
- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?
- A January to Remember
- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma
- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」