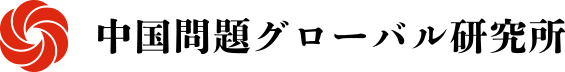アーサー・ウォルドロン
2019年7月
現在、中国と世界の多くの国々との間で繰り広げられている関税戦争には、基本的に中国が自国の経済力を過大評価してきたという歴史がある。そして、この過大評価は続いている。中国政府にとっては青天の霹靂であるが、米国が中国の輸出品に関税を課し、実質的な被害をもたらしたことにより、客観的な状況が根本的に変化した。
ここで二つの問いが特に重要である。第一に、世界第二の経済大国とされてきた輝かしい中国経済に、新たな関税やその他の措置はどのような影響を与えたか。第二に、貿易規制の変更は、一見、無関係な分野にどのような波及効果をもたしたのか。
これは、2018年に、貿易の均衡を図るために、恒久的な解決策を見つける交渉が行われていたにもかかわらず、トランプ大統領が中国からの輸入品に対して大幅な関税の引き上げを行ったことから始まっている。
米中の専門家は、何か月にもわたり慎重な交渉を重ねてきた。2019年序盤、新経済協定草案の合意は間近であった。
しかし、この草案がほぼ即座に却下されたことから、中国指導部は、自国の交渉担当者が何を案じていたかを詳細に把握していなかったことが見てとれる。指導部は、最重要箇所をいとも簡単に塗りつぶしたため、合意内容は骨抜きとなった。彼らは議論内容を認識していなかったのだろうか。
その後、重要かつ拘束力のある条項を削除したものが米国に送られた。2019年5月10日、トランプ政権は骨抜きの協定は受け入れられないと判断し、米中貿易政策は空白状態に陥った。そして、中国にはさまざまなかなり厳しい関税が課されることとなる。この強硬姿勢は中国政府にとって、突然の出来事であった。それは40年以上にわたってアメリカが中国に対して決してとるはずのない態度だったからである。
トランプ政権以前のアメリカの三政権であれば、いずれも「本当に重要なのは善意だ。将来の関係を改善するために短期的にこれを受け入れよう」と言ったのではないかと想像できる。最低でも、今まで通りの反応を中国は確実に期待していた。なぜなら、1979年に中国との関係が樹立され、1970年代以降の事実上すべてのアメリカ政権は、そうした姿勢を示してきたからである。長期的な「関係構築」と中国の侵害行為の容認こそが、最終的には中国を世界システムに参加させる方法だと考えられていた。
しかし、ドナルド・トランプ氏の見方は違った。彼が専門知識を有する唯一の分野である不動産の厳しい世界では、ルールは「約束は守るべきである」の一言と言える。もちろん、長い交渉が失敗に終わることも多いが、その場合、真の権力者である不動産所有者は、初日から弁護士らと調整しながら、物事の経過を綿密に追う。
トランプ政権側は誠実に交渉してきた。米国の一流の専門家が、次々と作成される協定草案を吟味し、承諾した。それにもかかわらず、習近平国家主席が容易に終身支配者に成りあがったのと同様、両国の交渉担当者の努力はいとも簡単に破棄された。彼は単に中華人民共和国憲法の一部を消去し、新しい文言を加えただけだった。何か月にもおよぶ慎重な作業を簡単に却下したことは、アメリカと中国両国の交渉担当者に対する侮辱である。
最も重要なことは、トランプ氏が裏切られたと感じたことだ。ビジネスではよくあることだが、トランプ氏は習近平氏と個人的な関係を築こうとした。技術的な問題を克服するために、良好な人間関係がもたらす効力を大いに信じたのだ。その意味では、習主席は友人ではないことが判明した。米国の政治家を操ることに慣れていた中国は、これまでと同様、米国は譲歩するだろうと考えていた。
この思いこみはすでに揺らいでおり、すぐにでも崩れそうだということを中国は理解すべきだったのだ。米国の歴史に対する理解が薄いことに加え、複雑な意思決定プロセスを有する中国は、40年間常に好意的であった米国の態度が変わることを想像できなかった。しかし、米国が操作されている、または真剣に受け止められていない、危険にさらされているという意見に最終的に達した場合、それまでの政策を突如覆すというパターンが繰り返されることを、アメリカの歴史を知る者は認識している。
つまりトランプ氏は、不動産業界の人々のように行動した。彼は、対話をやめ、以前の交渉相手に経済的な制裁を課したのである。この予想外の強気な姿勢は打撃を与えた。今日の中国経済は、米国経済とは異なる形で困難に直面している。そこで、貿易は公正でなければならないという新しい合意が生まれた。これはおそらく、トランプ氏が中国の軍事情報機関ファーウェイ(言うまでもなく「民間企業」ではない。民間企業というものは中国には存在しない)に対してとった制限の緩和を無効にするという2019年7月16日の米議会投票で最も明確に示されただろう 。
トランプ氏にとってこれらの譲歩は「餌付け」であり、米国が合理的で、寛大でさえあることを中国に示すためのものだった。しかし議会の見解は違った。もしファーウェイが米国の技術を盗み、自分たちのインターネット・システムに盗聴器を仕掛けていたとすれば、それに対して与える打撃は最大とするべきだ。すなわち、容易には回避できない徹底的な制裁という意味である。これらに加え、調査により、ファーウェイが中国企業の少なくとも半数と同様に、事実上政府の一部であるというという繋がりが明らかになった。
*
こうした簡単な歴史的背景から、中国の経済成長の性質とその効果という点に目を向けてみる。
中国はパラドックスである。国土面積では世界第三の規模(ロシアとカナダに次ぐ)を有するが、経済政策としては輸出主導型の成長を採用してきた。これはシンガポールにも台湾にもあてはまる。世界市場は十分に規模が大きいため、これらの国で国民総生産に占める輸出の割合がかなり多くても(台湾の場合は70%、日本は約11%)、顕著な歪みが生じることはないからだ。この事実は現地市場の大きな不足を反映している。人口が多い国は、国内の購買力が高く、地産地消型の産業を発展させる傾向がある。そして生産性を理想的に向上させ、購買力をさらに高め、より国内に焦点を当てた投資を行う。そこで台湾の一人当たり国内総生産(名目:すなわち、無限に柔軟な購買力平価(PPP)ではなく、貨幣量や為替レートを用いて判断すること)が1970年初頭の900米ドルから現在の26,000米ドル近くにまで押し上げられたようなプラスのサイクルが生じる。
1976年に毛沢東が死去した後、私有財産のない中国では、国内の民間需要は存在せず、中国政府は経済を成長させるべく決断した。靴の小売から鉄鋼生産まで、すべてを政府が行っていた。土地もすべて政府が所有し(これは現在も変わらない)、貧困状態にある農民が耕作しているため、需要はほとんどなかった。(今日、中国は何百万人もの人々を貧困から救い出したと豪語しているが、中国では貧困は年間約500米ドル以下の収入と定義されていることを考えると、それほど目覚ましい成果とはいえないだろう。)上述の諸国と同様に、中国は成長の原動力を外国の需要に依存しなければならなかった。これは、中国が社会をどうにかして変化させ、国から得るのではない民衆の富を得られるようになるまで続いた。現状では、中国の人口の半分以下が事実上、国のすべての富を占有している。
計画経済およびすべてが国有である現状を事実上廃止することは、共産主義体制や非効率的な国家統制経済の終焉を意味するだろう。しかし、それよりも簡単な道は、根本的な構造改革なしに、外国の需要に頼って中国経済を回復させることではないだろうか。それに加えて、中国の労働力の安さもある。
輸出向けの製造が時代の流れとなり、中国製品が米国をはじめとする海外市場にあふれ始めた。当然中国は、人口が多いというだけで大国であり続けた。GDPの半分以上は国内起源であったが、多くの場合は国際市場がない地元の必需品である。
発展が最も速かったのは、香港の豊かな自由経済に近く、長きにわたる貿易の伝統による恩恵を受ける南東部の広州(広東)周辺である。東莞周辺には、簡易的なつくりの工場が乱立し、主にウォルマートのような巨大なアメリカのディスカウント業者向けに大量生産を行った。
外国の顧客が、調達した商品の原産地や、質の低さを理解することはほとんどなかった。米国の中国貿易仲介業者で作家のポール・ミドラー氏は著書の中で、自身の数え切れないほどの直接の工場訪問に基づき(2011年の「だまされて。‐涙のメイド・イン・チャイナ」を参照)、東莞や他の工場から輸入された美容製品の成分は「高級アロエクリーム」と謳っているが、実際はその記述とは何の関係もなく、アロエとは程遠い、むしろ不衛生な状態で製造された偽物だと記している。
その一方で、今思い返せば理解し難いことであるが、海外の生産者が生産拠点を中国に移し始めたのである。その多くは、光ファイバーや、コンピューターなどのハイテク関連であり、クリスマス・ライトの類や有害な歯磨き粉などのような従来のものではなかった。何十億ドルもの研究成果である自社の専有技術が、知らないうちに盗用されたことに、米国人はショックを受けた。もちろん、これは一部には中国の二面性が原因であるが、同時に見事なまでのアメリカ人の無知と愚かさによるものでもあった。
その結果、外国製品の生産は壊滅的な打撃を受け、工場は閉鎖され、中間層は失業状態に陥った。 そこに登場したのがトランプ氏だ。
*
トランプ氏の当選は、小さな島国からではなく、世界有数の経済大国からの輸入品の波によって生活水準が壊された多くの米国人によって後押しされた。トランプ氏の行動は、中国にとって、予想外であると同時に決定的だった。自らの手で、中国経済の全般的な危機につなげたともいえよう。
中国は、自国の経済成長は奇跡的であると主張する。しかし、現在の中国の一人当たり名目GDPは450米ドル程度と、世界の下位40%に位置し、ブラジルよりも少なく、ウルグアイの半分強だがパラグアイより上、といったところである。毛沢東時代の中国よりはましだが、他国を真に驚かすような奇跡ではない。
問題は、中国指導部がこれまでの成長の例、すなわち第二次世界大戦後のドイツの「経済の奇跡」、世界で最も有能かつ先進的な経済大国への日本の発展(戦後の欧米の共通認識は、日本は海外からの援助により無期限に成り立つというものだった)、そしてとりわけ韓国、台湾、香港、シンガポールを全く理解していないことである。
習近平氏の身の周りには、この状況を理解する世界で見ても一流の経済学者が何百人も働いている。しかし、共産党が彼らに意見を求めることはない。したがって、中国の成長を真に自立的なものにする根本的な改革が存在しない。
この短いエッセイの中では、解決しなければならない問題の一部を列挙することしかできない。資本配分は市場金利で決定するべきである。そうでなければ、配分の誤りが長期的には経済の歪みと機能不全につながっていく。共産党は自分たちの無能さをもう十分に示したのだから、土地と生産は私有化するべきである。中国の貨幣を兌換可能にしなければ、本当の貨幣価値を知ることは誰にもできず、貿易の障害となる。そしておそらく最も重要なのは、政府の借り入れによる成長は終わらせなければならないということだ。あるいは「終わることになるはず」と言うべきかもしれない。GDPの400%程度の債務を抱えていれば、避けられない破産や銀行破綻などを通じて債務は自ずと清算されるだろう。中国は何度か乱脈融資によって経済を押し上げ、銀行は実質的に破綻状態に陥ったが、政府によって救済された。今日、中国は史上最悪の状況にありながら、もはやこれ以上先延ばしすらできなくなった差し迫った危機という底なしの穴に政府が生み出す資金を注ぎ込み続けている。
国による経営や共産主義経済は長期的には機能せず、結局は自滅するため、その報いは自然の成り行きだ。必要なのは改革であり、対処療法ではない。しかし、政治的には、中国政府はこの状況を継続できると信じているようだ。それでは、定期的な経済危機や効果のない、あるいは混乱を招く反応が常となってしまう。
共産主義体制には脆弱性が内在するが、中国は、先進国から数十億ドルもの海外直接投資を吸い上げる一方で(このような奇妙な意思決定をする国があるのかは謎だが)、米国の雇用と引き換えに、規制されていない米国市場への輸出を増やすことができるかぎり、成長を持続させることができる。トランプ氏は、中国の歪んだ経済システムを作り出したわけではないが、公正さ、均衡、合法性を予想外に主張する姿は、警察が突然違法カジノに入ってきたときにギャンブラーが感じるような衝撃を中国にもたらした。
*
では、中国および世界にはどのような影響があるのだろうか。
中国の外交は、長期にわたり外国の役人に賄賂を贈ったり、貧しい政府に金を貸したりする無限の資金を以て、資金の受領者を罠にはめてきた。返済できなければ、港湾などの資産を中国に明け渡さなければならない。推定では、少なくとも1000億ドルがこうした用途に使われている。この資金が資本不足の中国になぜ投資されないのかを考えるまでもなく(おそらく、多くは偽装された国外への資本流出である)、中国の人民元外交が困難に陥ることは間違いない。
2049年までに中国を世界最強の国にすることが表向きの目的である中国の巨大な軍備増強計画も同じである。他国を強制しようとする試みが、おそらくほとんどの場合には自殺行為に近い恐ろしい戦争へとつながるであろう世界において、「力」をどのように理解しているかを考えるべきである。中国はすでに、軍事設備に巨額の投資を行っており、この設備が非常に優れている点に世界の他の国々は脅威を感じている。この動きは中国海軍が世界中に基地を建設し始めたことで知られるようになった。こうした軍隊の維持に必要なコストは、研究開発費を除いてもすでにかなりの額にのぼる。軍隊を動かすことに伴う致命的な危険を考えると、現在の大規模な軍備拡大はそれらが使用されないまま宝の持ち腐れになる可能性が高い。
しかし、最も差し迫った問題は国内にある。外国からの投資が撤回され、工場は閉鎖、他国における生産チェーンが再編されている。中国は実際、輸出競争をしている他の国と差別化するようなものを何も提供していない。
巨大な人口は、政府によって一定の生活水準と退職後の生活を約束されている(これは都市部でのことで、農民は実質的に自助努力となる)。アメリカの社会保障やメディケア制度以上に、これらの約束がどのように守られるかは誰にもわからない。現時点で考えられる唯一の方法は、約束された金額を給付できるよう通貨を膨張させ、購買力のない通貨にすることである。
この解決不能な問題の結果として、不穏な状況を迎えた後、異なる解決策を推進する競合派閥へと党の分裂が徐々に進むだろう。ゴルバチョフがソ連の実権を握った時に直面した状況と似ている。国の終わりは、欧米では通常「崩壊」と呼ばれているが、それをおそらく最も熟知しているロシア人や中国人は、その言葉を使わない。ロシア語ではraspad「распад」、中国語ではjieti「解体」で、どちらも「分解」と解釈する。 中国が、「中国」として残ったとしても、構成要素が徐々に分解していくのをどのように回避できるのかはわからない。20世紀初頭の中国で最も著名な学者だった胡適(1891-1962)の先見の明のある言葉を思い出してみる。(※訳注:胡適は1935年、中国はただ堪えて待っていればいずれ日本が自滅するという趣旨の評論を発表していた。)放っておいても中国は大戦の後に統一されたが、その後の中国の統一と標準化(習近平氏の政策などもそうである)に向けた試みは結局、分裂・分解へと向かっているようにみえる。KGBを有する主体として、ソ連は、あたかも最初から分裂する運命であったかのようだった。中国の地図には、分離線がすでに書かれているかのように見える。
次に、香港について触れる必要がある。中国が国民に望ましくない法律を強要しようとする試みに反対する前例のない大規模デモは、おそらくこの問題の最初の兆候である。政府側はこれを全く予期しておらず、考えていたよりも鎮火させることは難しそうである。北京派の政治家たちからしても、普通選挙権をめぐる基本的な要求が満たされない限りこうした事態は生じる。反面、中国はほとんど恐れていない。仮に、最高責任者が民主的に選出されたとしても、中国との良好な関係を維持しようと苦心するだろう。
中国政府は明らかに同様の見解を保持していないが、本文の執筆時点で、中央政府が全く何も行動していないことは、中国政府が何をすべきかわかっていないことを示唆している。最終的には「武力に訴える」必要があると言う人も多いだろう。これもまた、例えば1989年の天安門の大虐殺のように、世間知らずの抗議者たちが、人民軍が発砲するとは思わなかった事件よりも大変な問題となるだろう。実際、人民解放軍は強く反対していたことを、事件後30年が過ぎ、中国政府がついに何かが起こったということを認めたことで、我々も知ることができた。さらに、香港は中国にとって数兆ドルの価値がある。その香港を破壊することは上海に打撃を与えるより重大な結果をもたらすだろう。
著者自身も、故人となった最高位の元人民解放軍司令官を儀礼訪問した際、間接的に同じことを言われた。すなわち、党は軍隊を頼れないということで、これは今後起こりうる問題の基になるだろう。
*
では、関税戦争はどのように終わるのだろうか。中国は譲歩案を見つけるよりも、交渉における立場を軽率にも固定化したため、暫定協定のような解決ではなく、ストライキと反撃がますます激しくなることが予想され、中国が状況をコントロールできなくなるだろう。
中国の制度が世界の貿易制度と両立しないことにより、中国は常に、特別な処置がなされた場合のみ、世界経済に参加することができた。中国は外国製品を輸入し模倣するというソ連が決していしなかったことをしているが、中国の構造を支える梁である基本的な経済構造は依然として1950年のソ連時代のものである。自由経済は、どのレベルであってもそうしたシステムと相互作用することはできない。これは、異なるねじ山を有するパイプを螺合したり、AC電流とDC電流を混合したりできないのと同じである。中国は、真に自由な市場経済になるように改変するか、それとも徐々に遅れをとるかの選択を迫られるだろう。
トランプ氏はThe Art of the Deal(トランプ自伝、「取引の芸術」、1987年)で有名である。彼が知るのはここに書かれていることのみであり、国際政治ではない。しかし、トランプ氏は中国から学んでいる。かつてトランプ氏が、米中両国の納得がいくような解決を望んでいたことは知られていた。しかし今や習近平氏に裏切られ、友情も冷めてしまったようだ。習近平氏が中国経済に世界経済との互換性をもたせたいと思っていても、彼では実現できないかもしれないことを、トランプ氏は一層理解するようになった。そうなればトランプ氏は、自分の意志ではなく、遠い将来に向けた協力を推し進める一方で、中国の違法な活動に対してより多くの関税と一般的な制限を課すだろう。
関税は貿易問題の最適な解決策ではない。しかし、インセンティブや取引パターンは劇的に変化する。この場合、彼らは中国に損害を与えており、中国にはこれに対処する効果的な方法がない。未解決の問題が長引けば長引くほど、世界経済の構造が変化し、中国は隅に追いやられる。中国の「台頭」は、正当化できない、自信過剰の時代からの、やや時代遅れの説得法と見られるだろう。
そうなれば、トランプ氏の関税(民主党による撤回もほぼ考えられない)は、アメリカの鉄鋼やその他の製品を保護する以上の役割を果たしたことが明らかになるだろう。この関税は、世界経済システムの基本的な透明化と変化を加速させ、公正さ、合法性、透明性への道を拓いた。
(この評論は7月18日に執筆)
カテゴリー
最近の投稿
- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機
- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ
- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?
- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!
- A January to Remember
- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma
- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」
- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?
- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く
- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く