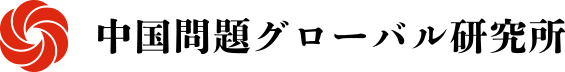誕生を祝して
数週間前、習近平の代名詞とも言える地政学的プロジェクトの10周年を記念する、第3回一帯一路フォーラム(BARF)が北京で開催された。フォーラムには22人の国家元首と140か国の代表が参加したが、代表者の多くは比較的低いランクの政府高官であり、一部の国々ではメディア関係者のみの参加となった。国家元首22人というのは結構な数にも聞こえるが、前回2019年の開催時より14人も減っている。
一帯一路とは何であるかを端的に表現するなら、それは中国と世界150か国を結ぶ約1兆ドル規模のインフラプロジェクトである。計画の実行開始から10年を経た今、その成功如何を問うてみる価値はあるだろう。一帯一路の目標は達成できたのか? この10年間で一帯一路はどう変わったのか? 世界の指導者たちの出席率が大幅に低下したことを、どう解釈するべきか?
答えは簡単ではない。そもそも、一帯一路プロジェクト全体が明確に定義されたことはなく、その名称さえもやや誤解を招きやすい代物であるからだ。一帯一路はしばしば、古代シルクロードの現代版として紹介される。この言葉は19世紀後半にあるドイツ人によって初めて使われたもので、王朝時代の中国と中東・ヨーロッパを結んでいた、中央アジアを横断する交易路のネットワークを指している。しかし、一帯一路における「路」とは陸路ではなく海路を指しており、「帯」とはアジア大陸を横断する鉄道と道路によって形成される経済ベルトを略したものである。そもそも、習近平のプロジェクトは別の名前で呼ばれており、10年前には、漢字の一路一带を直訳しただけの「One Belt, One Road」または「OBOR」という、かなり不格好な名称が使われていた。それに、中国がグローバル規模の投資に乗り出したのは今回が初めてではない。習近平が一帯一路について語り始める少なくとも10年前から、中国は多くの途上国に対してインフラ投資を行ってきたが、実績のほどはと言えば必ずしも芳しいものではなかった。これら初期のプロジェクトは一帯一路のスローガンの傘の下に行われたが、一帯一路プロジェクトの何たるかが明確にされることはほとんどなかった。過去10年間の活動で特徴的だったのは、各国が一帯一路の名のもとに中国と正式に覚書を交わすようになったことだ。これらの覚書は詳細が曖昧であったり、さらに心配なことに秘密裏に交わされたりする場合も多く、それほどの多額の投資の始まりとしてはいかにも頼りない。それでも、2018年半ばの70か国を大きく上回る約140か国が中国と覚書を交わしている。プロジェクトが明瞭なものではないにもかかわらず、ほとんどの途上国がここに一枚噛むことを望んだのであった。曖昧だった詳細も、いつかは明らかになるのだろう。
一帯一路プロジェクトの恩恵を受けられるのは、覚書を通じて中国と協定を結んだ国だけであり、中国が長年かけて示してきたことがあるとすれば、それはインフラを建設できるということだ。一帯一路とは実質的には、中国国内経済で持て余していたインフラ建設能力の輸出であった。時としてBRIは中国から世界への贈り物だとされることもあったが、実際には贈り物などではなく、すべて借金で行われたものだった。
モルディブの橋からパキスタンの発電所や高速道路、アフリカの鉄道に至るまで、被援助国は空港、高速道路、橋、発電所、地下鉄、電気通信などさまざまなプロジェクトのために中国の銀行から資金を借り入れ、プロジェクトの建設は中国の請負業者が担当する、というのが常だった。伝統的に借入へのアクセスが限られていた資金難の国々への融資も受け入れる、という中国の申し出は、断るには惜しいものだった。世界銀行や米国、EUといった他の貸し手とは異なり、他国の問題には干渉しないという中国の方針もあって、一帯一路という安全な傘の下で汚職が蔓延することとなった。中国国内の開発事業は汚職と切っては切れない関係にあり、現地関係者への賄賂や買収はビジネス慣行の一部となっていた。中国が契約に関する秘密保持を求めるようになると、汚職が横行するようになったばかりか、将来の需要や収益予測も極端に楽観的なものとなった。つまり、取引額が高騰して、被援助国がより多くの負債を抱えることとなった。短期的な影響だけを見て、「アメリカからは講義を受け、中国からは鉄道を得る」という捉え方がなされた。
橋や有料道路の建設資金を借り入れ、借金は将来的に利用者から徴収する通行料で返済するというのは、新たなインフラを実現する方法としては申し分ない。だが、通行料が高すぎて地元の人々がとても道路を使えそうにない、つまり実質的に徴収不可能だとしたらどうだろう? 利用者数が当初の予測を大幅に下回ることもありうる。返済条件があまりに過酷で、10年後という現実的な期限ではなく、わずか5年で返済しなければならなかったとしたら? 中国とヨーロッパを結ぶ数千キロの鉄道線路というのはいかにもインパクトが大きい話であるが、果たしてそれは経済的に実行可能で、航空貨物のスピードや海上輸送の膨大な輸送量に太刀打ちできるものだろうか? 多くの国々にとって、真新しい巨大なインフラは祝福どころか大きな問題へと簡単になり得るのだ。
こうした問題は中国国内では日常茶飯事であり、やはり過度に楽観的なプロジェクト展望がインフラの大規模な供給過剰を招いている。中国ににある数万キロの高速鉄道路線のうち、建設費の回収どころかランニングコストをまかなえるほどの採算が取れている路線はごくわずかだ。
では、全体的には成功と言えるか否か? 一帯一路は一度たりとも、実際の目標や測定可能なターゲットのある定義の明確なプログラムであったことはなく、成功と思ったもの勝ちという側面がある。たしかに数多くの覚書に調印がなされ、大量のコンクリートが打ち込まれ、取引こそ完了したものの、当初の投資への期待は多くの国々で実現しなかった。それでも、一帯一路の性質がどういう変化を遂げたか、同プログラムがもたらした意図せざる結果に対して北京がいかなる対応を強いられてきたかが、この10年間で明らかとなってきた。それを、ここから検討してみよう。
一帯一路が迎えた変化と課題
一帯一路が多くの途上国にとって魅力的に映り、より伝統的な借款や援助のルートと大きく異なっていた点は、中国側が現地の政治への「不干渉」を強調したことだ。プロジェクトへの資金提供の見返りとして、経済的・民主的プロセスや制度の改革が求められることはなかった。こうした紐付きでないアプローチは、融資の規模の大きさがゆえに中国の影響力と融資が各国の内政問題に発展し、何度も失敗の道をたどることとなった。ザンビア、モルディブ、スリランカ、ネパール、フィリピン、いずれの国においても、中国の投資規模に関連する問題をめぐって国内政治に対立が生まれた。中国は不干渉の方針を取ったに過ぎないと主張するだろうが、一帯一路の影響の大きさからすれば、それが参加国の国内政治の中核に関わっていることは間違いない。
借金の返済実績の乏しい国々にも大規模な融資を行ったことで、中国は多くの欧米諸国が以前から認識していたものと同じ問題に直面することとなった。一帯一路が始まった当初、返済リスクに対して中国は敢えて目をつぶっているように見えた。多くの取引が秘密裏に行われ、中国による融資の全容は開示されなかった。必然とも言えるように、スリランカのような国々が債務返済に苦しみ、世界銀行やIMFに救いの手を求めたときにも、中国からの債務の規模が他の債権者に明かされることはなかった。また、中国が提示した債務条件は中国金融機関への支払いを優先させるものではないか、という懸念もあった。過去何度も債務再編措置を実施してきたパリクラブ(主要債権国会合)でさえも、中国の債務を交渉プロセスに組み込むのには苦労している。すべての債権者にとって公平かつ公正な解決策を見つける作業への協力に、中国が消極的であったからだ。
一帯一路を批判する者たちはしばしば、その債務規模の大きさから返済が果たされないことはほぼ確実であり、支払いの代償として北京が当該国の重要な資産を掌握できるようになるため、被援助国を債務の罠にはめることになる、と主張してきた。同プログラムに対する評価としては厳しすぎるものであるが、伝統的なルートから外れた追加債務の存在が、やがてはプロジェクトの未完遂、中国への多額の債務、そして、はるかに大きく組織化された相手国に抵抗する術をほとんど持たないという無力さを突きつけ、弱い立場に各国を立たせることになるのは火を見るよりも明らかだ。
一帯一路プログラムから離脱した国はごくわずかだが、直近の離脱国であるイタリアとフィリピンへの注目度は高く、両国が経験した事例は、当初の期待に対して冷静な現実を突きつけるものだった。フィリピンでは注目度の高いプロジェクトの多くが軌道に乗ることなく終わり、中国側からの資金援助も実現しなかった。イタリアでは目立ったプロジェクトこそなかったものの、対中貿易赤字は中国に有利な形で膨らみ、中国が好んで使う「ウィンウィンの協力」(「合作共赢」)は欠片も見られなかった。先日のサミットでは、フィリピンのマルコス大統領は出席したが、イタリアは不参加であった。そのフィリピンでは中国の投資が反故になったばかりか、中国によるフィリピンの領海侵犯が続き、海軍や地元の漁師を脅かし続けている。世界での経済的なウィン・ウィンの関係をもってしても、悪化の一途をたどる南シナ海の地政学的状況を覆い隠すことはできない。
それでも、習近平が一帯一路に見る未来は明るい。彼の親友であり、先の一帯一路フォーラムにも参加したウラジーミル・プーチンは、農業やパイプラインへの中国からの新たな投資の確保に失敗したが、同プロジェクトにこれ以上ない高評価を与えた。初期に見られた乱暴な融資や楽観主義は過去のものとなり、中国の融資は劇的に鈍化した。2018年以降、中国は2,400億米ドルを超える一帯一路関連債務の再編を余儀なくされたという報告もある。こうした厳しい経済状況下において、中国は新たな困難に対応し、適応してきた。
経済・貿易インフラが一帯一路の肝であることに変わりはないが、先のフォーラムで習近平は一帯一路を米国主導の西側諸国に対する地政学的対立軸として捉え直そうとしていた。ロシアと中国の際限なき友好関係は変わらずこの中心にあり、両首脳はほぼあらゆる国際的な話題において米国を批判し、ロシアとウクライナの戦争、ハマスとイスラエルの戦争、そのほか世界が直面しているあらゆる危機の責任が米国にあるとして憚らなかった。両首脳にとって、自分たちの対峙する相手が西側諸国であることは明白だが、国家間の関係における「力こそ正義」という冷徹なアプローチの先に、実際に何を見据えているかは明確には見えてこない。習近平は、中国の発展と中国の文明が他国の模範となるのだという姿勢を隠そうともしてこなかったし、一帯一路は習近平が「グローバル安全保障イニシアティブ(Global Security Initiative、GSI)」、「グローバル発展イニシアティブ(Global Development Initiative、GDI)」「グローバル文明イニシアティブ(Global Civilization Initiative、GCI)」と呼ぶ大きな構想のパターンにも当てはまる。だが、一帯一路の恩恵を受けている国々も含めた各国首脳は、習近平やプーチンの世界観に心から賛同しているのだろうか? それを見極めるのは難しいが、各国首脳の一帯一路フォーラムへの参加人数が減少しているという事実はおそらく、途上国側も中国のインフラに興味はあれど、中国の思想や統治にはさほど関心がないことを良く示す兆しだろう。
習近平は中国社会と中国共産党の中枢にイデオロギーを呼び戻したが、同時に、環境の要求に応じて適応できることも示した。一帯一路は融資の規模を縮小し、単に経済的なものという範疇を超えて、欧米に対抗する地政学的な対立軸を築くためのより広範な政治的イニシアティブの一部となった。一帯一路は過去のものとなるわけではなく、一部の人々の期待通りの成功こそ収めはしなかったが、新たなものへと姿を変えた。今後10年間は、習近平の描いた未来像が、彼の抱える資金の魅力ほどに多くの国々を惹きつけられるかどうかが試されるだろう。
カテゴリー
最近の投稿
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ
- 記憶に残る1月
- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機
- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ
- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?
- A January to Remember
- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma
- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」
- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?
- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く