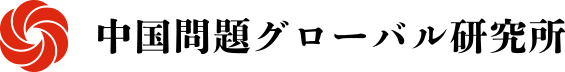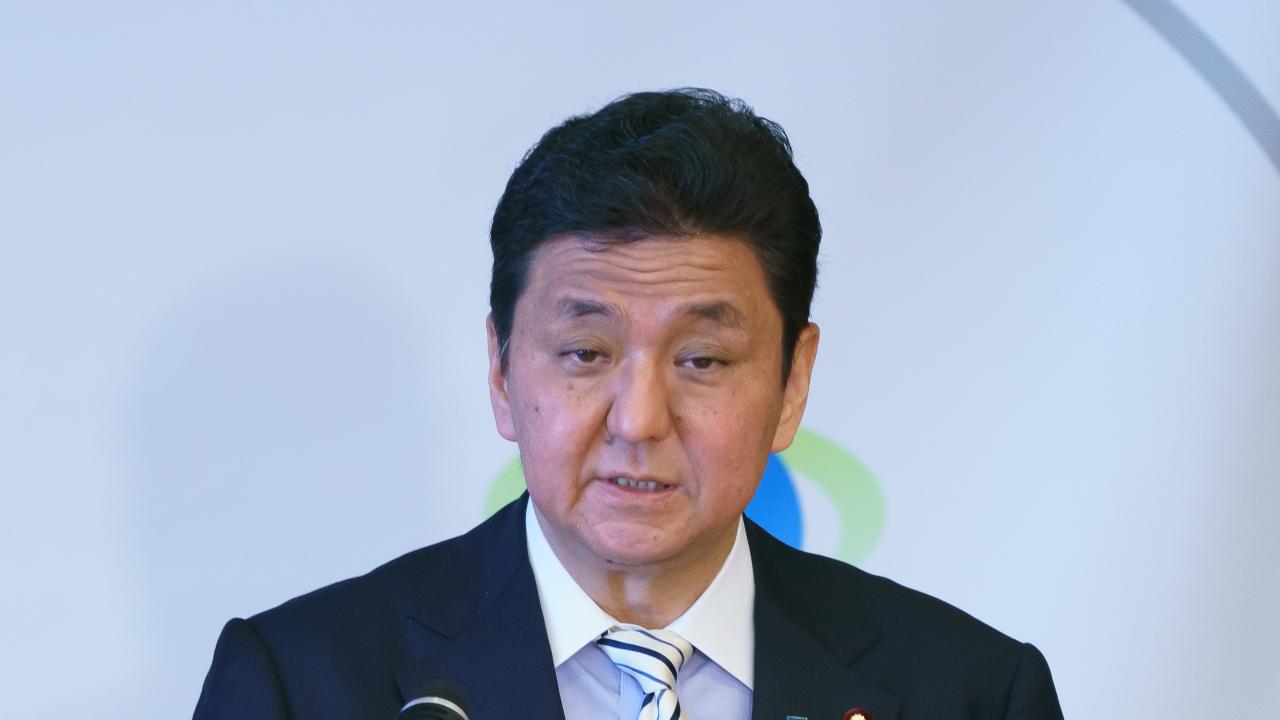
中国の共産主義者がアジアで紛争を始めるかもしれないことに、私は初めて骨の髄まで戦慄を覚えている。情報の上ではその可能性について40年間にわたって認識してきた。そしてそのような惨事を防ぐための強力な抑止力を常に強く唱えてきた。しかし、危機は予期していなかった。
ここ数カ月で何かが変わり、深刻な可能性は迫り来る危機へと転換した。中国の共産主義者の振る舞いは、極めて挑戦的でかつ妄信と強引さを伴うものであり、私でさえ驚き、今は懸念を抱いている。
今や多くの日本人が、おそらく米国政府よりも私の懸念を共有していると考えている。
麻生太郎副首相(1940年~)は7月6日(米国時間)、この懸念を簡潔かつ注意深い言葉で認めた。既に誰もが知っている以上のことを言ったわけではなく、中国の大規模で急速な軍備増強はとりわけ日本にとって脅威だと指摘した。また地図を一目見れば明白な事実についても、麻生氏は同様に言及した。すなわち、中国共産党が地理的に日本と同じ群島の一部である台湾を攻撃すれば、文化的で知性が高く平和な国である今日の日本の存在に致命的な脅威になるということである。日本は自国の生存、そして日本がその中心で輝く自由なアジアの生存のため戦うほかに選択肢はないだろう。
麻生氏はもう一つの事実には触れなかった。きっと麻生氏も認識していることであり、私が日本の友人に可能な限り強く訴えている事実である。すなわち、米国が予測不可能な同盟国であるということだ。 同盟や連合の一員であることはこの上なく望ましいことだが、日本は必要であれば自らを単独で守る覚悟をしなければならない。その能力には必然的に適切な核能力が含まれる。
日英同盟(1902~23年)で保証された安定に終止符を打ったワシントン会議 (1921~22年) の後、四カ国条約や九カ国条約によって約束された多国間の安全保障協議は広範ではあるが実体がなかったため代替策とはならず、米国は不用意にかつ正確な情報のないまま中国に味方するようになった。それが日本の民主主義の流血を伴う破壊、そして戦争につながった。
この戦争の危険、そしてそれが次第に顕在化することは、 宇垣一成(1868~1956年)のような当時の思慮深い日本人の心をずっと占めていた。太平洋戦争とその余波がインド太平洋地域の政治的な構造を一変させたという見方もあるだろうが、そのような思いは常に存在してきた。そう。深層の構造はほとんど変わっていないのだ。実際、日本を無視して中国にすべてを賭けたニクソン・キッシンジャー政策の破滅的な誤算は、結果的に飢えた新しい覇権志向の国を生み出して終わったというのは、ある意味でこの歴史の空恐ろしい総括である。
もちろん日本は、1921~22年の新たな脆弱な民主主義国家から、1930年代と1940年代半ばの軍国主義的独裁国家、さらに現在の安定し長く確立された立憲国家へと変化している。公平にみて、日本が国を再建してきたのに対し、中国はおそらく後退しているだろう。これは私だけの見解ではない。共有する多くの中国人もいる。
中国共産党の創立百周年の祝賀行事があったばかりだが、この祭典には外国の要人が1人も出席しなかった。楊潔篪氏(1950年~)は闘志盛んな口汚い元外相で(私も時折議論してきた)、プーチン氏 (1952年~)が中国の緊密な同盟者であると主張してこの祭典に招こうと多大な努力を尽くしたが、したたかなロシア側はビデオ会議を通じての出席にとどまった。中国の言いなりだと誤解されている北朝鮮でさえ、仮に中国の友人ではないとしても、式典には出席しなかった。大々的に宣伝されたこの記念式典に外国人が全く出席しなかったことは、習近平国家主席(1953年~)とその仲間に心底から屈辱を与えるものだったと認識しなければならない。
なぜ誰も出席しなかったのか。理由は簡単だ。中国の侵略的な外交政策と辛辣なレトリックがますます強まっているため、世界のほとんどの国が距離を置き始めているからだ。例えば、ドイツは中国に対して友好的な傾向がある。米国政府の言いなりにならないのは確かだ。しかし、ドイツは予定されているインド太平洋演習に海軍部隊を派遣している。これを巡り中国の外交当局者がドイツ国防省を脅した時、ドイツ側は予想に反して引き下がりはしなかった。むしろドイツは中国が国際法を順守しなければならないと主張した。特に常設仲裁裁判所が2016年に、中国の海洋権益の主張や拡大は国際海洋法条約の下で違法と判断した拘束力のある判決に従わなければならないと主張した。同条約は中国も署名しているからだ…。このことで私は国際連盟の決定を思い起こす。国際連盟は中国も日本もその権威を認めた国際的な法的機関で、1933年に日本に対し満州からの撤退を命じた。この決定は強制執行することはできず、代わりに日本が1933年に国際連盟を脱退した。
今日、中国は日本の1930年代の台本をなぞっている。(自らも管轄権を認める)裁判所の判断は全く意に介さず、おそらく、世界122カ国が認識しているこの大きな法的な敗北はいずれ忘れられると無分別に想像しているのだろう。あるいは(当時の日本のように)、中国の強大な軍事力は、ハーグの平和宮にある常設仲裁裁判所で裁判官が紙に書いた判決に優るとも劣らないと思っているのだろう。これは、約1世紀前に日本が国際連盟を無視したのと同じくらいひどい過ちである。
実際のところは中国の過ちの方がひどい。
まず、今日では強制執行のメカニズムが存在する。米国のブリンケン国務長官 (1962年~) は、中国がフィリピンに対して国際法違反を続けていることは、フィリピンと米国との同盟(1951年、2014年)における防衛条項の発動につながると述べている。これは深刻な問題だ。平和を望みながらも戦争の防ぎ方をほとんど知らないブリンケン氏にとっても、また中国共産党にとっても、同じように歓迎されないことだろう。
第二に、中国共産党は強大な軍事力を保有してはいるが、オーストラリア、インド、日本、米国が巧みに育てた「クワッド」(「4」の意)の同盟には及ばない。クワッドは前米国務長官のマイケル・ポンペオ氏(1963年~)の静かな尽力によるもので、私はポンペオ氏の国務長官としての功績はジョン・クインシー・アダムズ元長官(1817年~1825年に在職)に次ぐものだと考えている。
こうした現実があるため、中国は前世紀の日本のようには戦争に訴えることはないだろう。中国は国際法に違反しているだけでなく、国際社会がほぼ一致して中国の政策に反対している。反対の意思は堅固なものである。
しかし非常に厄介な問題が1つ残っている。核抑止力である。中国共産党の危険な路線の継続を防げるのは、核戦争に対する真の恐怖のみだと私は強く確信している。しかし、クワッドの中で核兵器を保有しているのはインドと米国だけだ。インドや米国は、中国がその核兵器を行使して恐ろしい報復に出ることを考えた場合、日本を守るために核兵器を使うだろうか。
私はインドの代弁はできないが、そうはしないだろうと思う。米国に関しては、日米安保条約の内容がどうであれ、米国が日本を守るために核戦争に突入することはないと確信している。誤解のないよう付け加えておきたいのは、米国がたとえ1つか2つの核爆弾で自国の領土に攻撃を受けたとしても、直ちに核報復を行うという確信を私は持っていない。 クリントン元大統領 (1946年~) やオバマ元大統領 (1961年~) が、このような状況の下で数十発の核攻撃を仕掛けることを現実的に想像できるだろうか。それはないだろう。それが正しい。米国が攻撃を受けた後の瞬間は、人類が自爆による壊滅から自らを守る最後の機会となるからだ。最善の道は即時発射態勢の運用かもしれないが、世界を地獄の淵から引き戻すにはまずは緊急外交を展開することだ。
しかし、日本の安全保障政策は私たちが無分別に約束したように、米国が日本を守るという誤った考えに基づいている。しかし、米国の保証は日英同盟と同じくらいはかないものになるかもしれない。
こうした歴史があり、また日本が現在の明白な危険を認識しているのであれば、日本政府は何をすべきなのか。
数年前、私は日本大使を夕食に招待した。私はいつものように、これまで述べてきた懸念を彼に説明した。良くも悪くもこの考えは何十年もの思考と経験の産物である。恐怖が本質的に抑止力の基本である。私は中国の共産主義者は日本を恐れていない一方で自らを過大評価しており、何らかの軍事行動を企てる可能性がある。その場合、極めて賢明な安全保障研究者の1人であるジェームズ・ファネル大佐(米海軍を退役)が述べたように、おそらく「短時間の鋭い打撃」を尖閣諸島に加えるかもしれないという結論に至った。大使は当惑していた。そして「間違いなく中国は私たちが核保有国の戸口にいることを理解していますよね」と答えた。 私は分からないと応じざるを得なかった。
中国の歴史の記憶はプロパガンダの幻想に満ちている。世界の芸術の多くは戦争の恐怖を自国に伝えた。例えばエーリヒ・マリア・レマルク (1898年-1970年)の「西部戦線異状なし 」(1929年) のようにだ。しかし中国は違う。誠実な戦争小説の痛みではなく、楊沫 (1914年~1995年)の小説「青春之歌」(1958年)のように想像上のヒロイズムをロマンチックに描いた。張正隆(1947年~)の「雪白血紅」(1989年、その後発禁となる)はおそらく例外である。
宣伝者は自らの宣伝を信じるようになる。中国共産党の中には、円滑で無血の勝利が得られると実際に想像する者もいるのではないかと懸念している。私は何度か広島の被爆地を訪れてじっくり考えた。直近の訪問は、美術館に夢中になっていた10代の息子2人と一緒だった。私は当時から半分破壊されたままの建物の近くにただ座り、閃光、放射線の炸裂、爆発、衝撃波、空高く舞い上がるキノコ雲、そして犠牲者。そのすべてを想像した。大切な時間だった。訪問を勧めたい。
その日本大使に私が提案したことは何か。
第一に、フランスやイギリスが保有しているような潜水艦に搭載する最小限の核抑止力を直ちに開発すること。この軍事力の目的は、核戦争を起こすことではなくそれを防ぐことにある。この点はいくら強調してもし過ぎることはない。そのような抑止力は私たちが知る最強の予防策である。
第二に、メッセージを明確に伝えるため広島の原爆記念日である8月6日に、およそ12キロトンの核兵器を地下で爆発させること(広島を破壊した「リトルボーイ」は15キロトンだった)。地下と言ったが、中国人にとっては実際の爆風やキノコ雲を見て初めて実感や恐怖が生まれるだろう。したがって、放射性降下物や汚染の心配がないのなら、大気中で爆発させることを勧めたい。この小さなデモンストレーションには、平和の意思を示す誠意ある宣言が伴う必要がある。以上が私の大切なゲストに話したことだ。
この後の動きは簡単である。日本の軍事力の拡大、ただし過剰な拡大ではない。世界最高水準に匹敵する船舶、航空機、歩兵装備の製造。日本の優れた情報能力のさらなる向上。攻撃に抵抗するための基地と居留区の整備。
こうした基礎の上に、日本の外交や、世界との関わり、アジアをはじめとする諸外国の戦略的理由だけでなく人道的、文化的理由によるパートナーシップを一層発展させていくことを提案したい。何よりも自由と安定した平和を求めて、リーダーであるとともに良き同盟国になるための真の努力である。
10年前と比べると、中国共産党が手の内を見せているので、この課題は政治的に比較的容易になった。マレーシアは2021年6月1日、中国共産党の侵犯に対して自国の迎撃ジェット機を緊急発進させた。軍事大国ではなく内向きな国であるマレーシアがこうした必要性を感じていることからみれば、結局のところ、中国のやり方はあまりにも強引であり、ある意味でその表向きの目的には逆効果であることが確かだろう。(私自身の見解では、中国の外交政策は党内競争が原動力となっていて国民の注意をそらす狙いもあるが、それは別の論文に譲る)。
結論を言えば、最も難しいのは(最小限の)核の一線を超えることである。しかし時は来た。異論を唱える人もいるだろうが、真剣に考えれば途方もない破壊的な紛争よりも、信頼できる抑止力の方がより良い選択だと理解する人は多いだろう。
日英同盟を誤って解消したことが太平洋戦争を招いたが、これは日本にはコントロールできないことだった。戦争を排除しようとするなら、日本の最小限の核能力と強力な防衛軍事力、および強固な同盟関係が不可欠である。弱い日本は紛争を招く。この事実を決して忘れてはならない。逆に日本が核を持てば、すべての人の平和確保のため今日と比べものにならないほど私たちの距離は縮まるだろう。日英同盟は日本政府が何の影響も及ぼせず英国政府によって一方的に破棄されたが、核能力の問題の決定的な選択は日本政府にしかできない。言い逃れはできない。代替するものもない。
(最小限の) 核クラブに加入することは日本の義務である。実際にそれを選ぶかは日本次第である。世界の平和は日本の選択にかかっているかもしれない。
カテゴリー
最近の投稿
- Internationalizing the Renminbi
- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する
- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ
- 記憶に残る1月
- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機
- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ
- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?
- A January to Remember
- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma