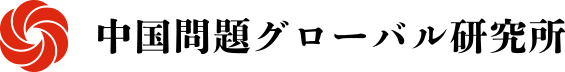中国ノート 2019
アーサー・ウォルドロン
2019年6月
概要
中国の外交政策は、国際動向による産物ではなく、中国国内政治の動向によるものである。我々はこれを念頭に、中国の軍事費の増大、国境侵犯、そして朝鮮戦争時並みの反米プロパガンダを分析する必要がある。
我々はアメリカ人である。我々は、世の中の出来事がアメリカのせいであると直感的に思ってしまう。中国人も、香港での動乱(2009年6月)を不特定の国外勢力によるものとする。多大な研究や出版物は未だにワシントンに鍵があると模索する。あの冷徹で冷酷な中国人らをヒステリックにさせるものを見つけようとするが、これは時間の無駄である。
中国の分析をするときに、我々はその混沌・残酷・マフィア的な中国政治の中にある根源を見つめることを学ぶべきである。レーニン(1870-1924)曰く、「誰が? 誰を?」(кто? Кого?)、これを忘れないようにしなければいけない。
毛沢東(1893-1976)の死後以来、中国国内政治は最も緊張感が高まっていると共に、中国が1950年代以来最も国際社会に対して敵対的な態度を取っている状況にあると思われる。彼らは豊かになり、そして一部の兵器開発(対艦ミサイルなど)において一歩先を行っている。70年代以降のアメリカにとっての外交の前提は、中国は友好的であることだったため、これらの展開に対して我々は衝撃を受けざるを得ない。
ここに書くことは、私なりにこれらの展開を理解しようと試みるものである。
I 診断
中国の外交政策が大胆に転換し、今やアメリカは不倶戴天の敵になった。この転換はいつ起こったのだろうか? 公式発表などを見る限り、習近平(1953-)政権より先立つものだが、2013年以降確実なものになった。政策転換の輪郭が見えたのは、1995年に中国が南沙諸島のミスチーフ礁をフィリピンから強奪したときであるが、それ以降は国内で蠢いていた。
2015年、中国は南洋(南シナ海)を主権の及ぶ領海・領土であると宣言し、ある種の国際デビューを果たそうとした。指導部が国内における権力基盤を盤石にするほか、人民からの支持を得るための国粋主義的なパフォーマンスと推測される。中国は、大国として勃興する際に隣国が屈服するであろうと期待した。そして、アメリカが予告なく舞台から降りた。ハーグの常設仲裁裁判所は、中国の行動が完全に違法であるという判決を2016年6月12日に下した。
二点注意することがある。一つ目は、フィリピンは屈せず、訴え出たこと。二つ目は、中国は完全にこの判決を無視したが、中国自身は仲裁裁判所の管轄内であると自ら宣言しておきながら無視することを決めたため、中国の国際的な立場を悪化させるとともに、中国の約束や署名にどのような拘束性があるのかを疑問視せざる得ない状況にした。この問題は永久に残ると共に、中国が例外であることは誰も認めないだろう。ナポレオン(1769-1821)は言った。「スペインは、余の潰瘍であった」、と。
これは中国にとって悪い兆候である。政治学者らは指摘するが、新興勢力に対して国家はバンドワゴン効果の如くバスに乗り遅れないようにするか、対抗的な連合を組む。学者らは、各国がどの選択肢をとるかまでは予言できない。しかし、あの判決を無視することを決めて3年たったいま、対抗的な連合を組む選択肢を取ったことは明白である。これは経済的な次元から、軍事政治的な次元にまで発展した。
現状分析の前に、中国の勃興について私見を述べさせていただきたい。ある中国の新聞の見出しに、「中国は来年(2020年)でアメリカのGDPを超え、世界の覇権を握るであろう」とあった。中国はカナダより少しだけ小さい広大な国であるが豊かな国ではない。一人当たりGDPはウルグアイの半分である(パラグアイより上だが)。中国は経済的な奇跡ではないのだ。
中国の指導者らはびっくりするほど経済に関して無知である。彼らは日本の第二次世界大戦後の復興の奇跡を理解していないし、韓国、シンガポール、台湾の経済的な奇跡もわかっていない。そして、毛沢東時代より、彼らの食卓がこんなにも豊かになったと自画自賛する。もし毛沢東が当時あった経済成長を破壊しなかったら、今や日本の経済と質的に並んでいたであろう。中国の経済成長は中国人自身と、一部の来訪者を驚愕させるが、学者らはあまり感心しない。皮肉にも、習主席の執務室から100マイル以内に1000人以上の世界クラスの経済学者がいるのにもかかわらず、意見を聞かず彼自身の考えと北京101中学で学んだことで政策を決めている(彼の高等教育は毛沢東の文化大革命下であり、清華大学が一応彼の履歴書に載るが、当時の清華大学はただの幼稚園である。彼の卒論はゴーストライターが書いた可能性が濃厚である)。結果として、彼の経済政策は紙の上でも矛盾だらけである。ソ連モデルを未だに経済政策の基礎構造としているため、経済的危機はそう遠くないことが明確である。
軍事的に、中国は世界最大の軍を建設しようとしている。未だに住宅・健康・食糧・さらに衣服でさえ問題を抱えているのにもかかわらずだ(ある考古学者が陝西省の僻遠の地で研究しているのだが、そこの住人は衣服なく裸で過ごしていると言う)。中国の軍事的プロジェクトは、(J-20、F-35のライバルになるように開発された)第五世代戦闘機のエンジントラブルが多発しているにしても、よく進んでいる。ここで、中国と戦争になる道を我々は辿っているのかという疑問が湧く。
領土とその強奪ぶりを見れば、そうであると言わざるを得ない。南洋(南シナ海)は地中海より5割大きい。中国はそこの航路と島々を支配下に置くために行動をしている。中国と戦争はしないと考えられるのは、アメリカ・日本の連合および、インド、ベトナムなど中国と陸で繋がっている14勢力のうち4つの国と地域だ(ただし、日本、台湾、フィリピン、インドネシアなど個別で国境に接していないところと戦争にならないとは言えない)。ドイツでさえ二正面作戦を維持することが叶わなかったのだから、中国があたかも朝鮮半島からヒマラヤまで、しかも一部核武装している国々に対して、纏めて勝利できるかと言えば無謀としか言えない。しかし、小さいことで急に紛争が勃発しないとは言えない上に、これが起きたらより大きい戦争になり、すべてが灰燼に帰すだろう。
合理的な説明としては、中国は尊敬されたいのである。そして、国際的にこれがなされていないと感じ、そして中国自身も理解していないが、恐ろしさを醸し出したいのだ。この恐ろしさ、「威」を出したいというのは基本中の基本である。中国は面子にこだわるもので、いままでは国内向けであったのが、いまや国際社会に向けられている。彼らはアメリカをナンバーワンと捉えているが、アメリカ自身、台湾より自由度が数段階落ち、報道の自由も最高ではなく、経済生産性が三位で、びっくりするほどの文盲率を誇り(著者はフィラデルフィアの住人で、アメリカにおける最高と最低の教育現場が隣接することが見える)、等々、そうそう良いという訳でもない。しかし、多くの中国人も賛成すると思うが、住むには悪いとは必ずしも言えない 。筆頭の国というものをどうやって測るのか? いちばん水爆を持っていること? これは馬鹿馬鹿しいことだが、中国の目的は、世界の法廷もNATOも誰もその行動を制限できなくなるまで強くなることにある。中国は注意深く、どこへでも航海し、ルールを破る。
Ⅱ 現時点におけるリスク
復習をすると、中国の外交政策は国外関連のものに対する野望などではなく、国内動向によって決定される。中国自身は、必要なものを手に入れることはできるし、アメリカの善き友になれない客観的な理由はない。実際、1950年代には、利益のためではなく思想的な理由でアメリカと接近した。よって、中国が示す問題の原因を国内に見る必要がある。
我々が前提として認めるべき事実は、中国は広大であるが、厳密なルールに基づいた法治国家ではなく、ルールに基づいた経済システムも有していない、ということだ。指導者がどのようにして選ばれるのかはなぞである。なぜ、ある経済政策が決定されるのかも、困惑しかない。中国はその歴史の中で、常に男性による専制政治であり(武則天(624-705)を除く)、1912年から1928年の間、専制政治から離れようとしたが失敗した(ロシア、ペルシア、オスマントルコでも似た試みがあった)。中国は一度たりとも法治国家になったことがないのである。
言い換えると、紀元前221年以降、中国は封建制度に移ったことがないため、フランスのような近代的な王政改革に踏み切ることはなかった。キッシンジャー(1923- )の最も大きな中国政策関連の間違いは、マルクス主義とアカ(共産主義)特有のチンプンカンプン(、、、、、、、、)の裏に近代化された国家があり、国際関係を問題なく泳げると思ったことである。
我々は、中国が近代化したことがないことを今更ながら発見したのである。通貨を本当に制限なく交換できるようにすれば崩壊するだろう。経済構成のうち、国有企業が4割から5割という状況下で、制限のない通貨になれば国際競争の中で直ぐにでも破綻するだろう。よって、これらを守るために軍事力があるのだ。更に加えると、中国の財政は完全に不透明で貧弱であり、膨れ上がりながら計測不能な借金、世界の中でも稀に見る生産性の低さ(インドは中国の2倍、日本は5倍の効率を誇る)であり、この「大帝国」は古(いにしえ)の時代の如く、瓦解するであろう。
北京はそもそも非正統であるという事実を抱えている。毛沢東がスターリン(1878-1953)になりきろうとして、ジョージ・マーシャル米将軍(1880-1959)と幾多の教養ある中国人の期待を裏切り、民主制導入の約束を反故にしたという過去がある。
2019年6月3日、大衆紙である『環球時報』が紙面いっぱい、これまで完全に検閲されていた天安門事件(1989年6月3-4日)について言及した。習主席はこの事件の対応を正当化しようとした。事件が起こったのは事実だが、これを弾圧していなければ国が崩壊していただろうと。どこで、どのような鎮圧が行われたのかの詳細には触れなかったため、読者は疑問が湧いたであろう。
国家が本当に危機に瀕していたのなら、軍は如何なる手段を以てでも弾圧を支持しただろう。だが、そうではなかった。北京に進撃することに賛成する部隊を探すのに苦労したことはすでに分かっている。7人ほどの司令官は、書面で反対した。1人は仮病を装い入院した。とある解放軍元帥(もう死去したが)が筆者に対して、他の元帥もこれに強く反対していたことを打ち明けたことがある。鄧小平(1904-1997)が相変わらずタバコを吸いながらブリッジを遊ぶだけで、正統の政府首班であった趙紫陽(1919-2005)が対応していたら流血を回避できただろう。軍が反発したのは、命令するのが戦士ではなく、ただの政治将校・人民委員(コミッサール)とその類であって、その無知を以て危機に突入していったことにある。
その支配が非正統である(そして広くそう見られている。もし、鋼鉄の如き独裁者であり、森羅万象が彼を恐れるのなら、あの素晴らしくて知能の低いくまのプーさんを、似ているからといって直ぐ検閲するのか?)がゆえに 、急な変化が起きてもおかしくない。
私は現代中国研究にありがちな予言(私は20世紀の専門であることに満足している)を避けるが、中国の党幹部は今の指導者を嫌っていることを確信している。彼のように見識がなく、あからさまな間違いを犯し、そして極め付けはあの個人崇拝である(偉大なる主席の一々の行動を、どれだけ注目しているのかを電子的に監視している)。主席の同僚ら全員が、党常務委員会で座ることすら叶わないと聞く。いつ継承危機、暗殺、クーデターが起こるのかが分からない。そしてそれが起きたら重大で取り返しのつかないことになるだろう。党の中の党が、その一体感を維持できなくなったらパズルの如くその国体が瓦解し、政府が常に恐れている軍や人民との不和が拡大する(ウェリントン公が指揮を執っている兵らを恐れたように)。2001年の海南島事件で米軍機が墜落した際、中央政府はまるで交渉ができず、結果的に人民解放軍が行ったが、これもよい結果にはならなかった。
中国が崩壊することは全くありえない出来事ではなく、実際、1991年12月25日(編注:ソビエト連邦が解体した日)に中国の元となるモデルが崩壊したようになる可能性を秘めている。あのとき、アメリカは行動しなかったが、今度中国が崩壊するときには、我々は迅速に行動する必要がある。
Ⅲ 処方箋
現状として、我々の態度は良いものであると考える。我々はやっと、中国を国際法・貿易制度を破る敵対的な国として、相応な政策を取り始めている。
我々は経済問題、軍事的な脅威、そして同盟国の利益を全部一つの問題として捉える必要がある。中国を今までのように空っぽな署名付きの約束で逃げさせるのではなく、強制的に屈させることができるだろう。
これを成すには、今の政治展開をいくばくか遅くさせる必要がある。我々は、問題解決には、中国の国内体制の完全な作り替えが必要であることを認めるべきである。これらをやらないと、経済問題のほかに、突発的な問題や事件に対する対応はできない(国務省は漸変主義を常に使っているが、これは失策である)。
中国は旧ソ連以上の進化はしないだろう。根本的な変化がないかぎり、中国に対する期待を減らし、旧ソ連との長い共生を目指すのが最適とも思える。
中国の地政学的なパターンとしては、常に増える負荷とストレスがかかる上に敵対的な国家に包囲されることが見られる(ロシアとの「蜜月」は一時的なものでしかないだろう。モスクワが、中国がウラジオストックとカムチャッカ近海を支配することを認めるだろうか? 否)。
忘れるべきではないのは日本である。我々は1920年代と30年代、そして70年代のように、日本に対して政策的に遅れをとるべきではない。ロナルド・レーガン(1911-2004)による訪問と国会での演説は、例外的な外交的な勝利だ。実際日本は、潜在的核保有国であり、100機以上のF-35を保有することになり、世界に冠たる非大気依存推進潜水艦を保有し、そして北京を神経質にさせる軍事的な準備と展開能力を有している。私自身の考えとして、2017年10月27日に安倍晋三(1954- )が再選を果たしたことが平和を保ったと確信する。これは賢いことではあるが、中国は日本を恐れている。
戦争をなるべく回避するには、同盟国に対して体系立てられた防衛と核兵器の拡散を促すべきだ。核兵器の不拡散にアメリカは力を入れているようだが、イギリスの提案を一回蹴り(編注:イギリスがアメリカに包括的核実験禁止条約に批准するよう勧めていることについて指していると思われる)、イスラエルについては沈黙を保っている。他の国では、核兵器を得ようとしたときには、あらゆる手法を使ってでも止めるにもかかわらず、である。
ワシントンがなにもできないまま、インドは勝手に核保有国にもなった。筆者はインドのジョージ・フェルナンデス大臣(1930-2019)から聞かされたが、ポカランⅡ核実験(1998)は、完全に中国向けのシグナルであり、中国による特に 1962年の(中印国境紛争にまで発展した)対インドの非常に近視眼的な政策に対する反応である。ポカランⅡの発表について、インド首相が許可したのは、ワシントンが、これをすべてパキスタンの仕業と仕立てようとしたためである。
現代においては、多くの国が当時のインドのように核を保有しないまま、敵対する可能性のある核保有国と対峙している状況にある。平和を保つには、日本・韓国・台湾は核兵器を保有する必要がある。ベトナムや他の国も皆が思っているより核保有に近づいている(台湾について、2回ほど強制的に止めさせたが、9ヶ月あれば完成するとある将軍は言う)。我々の最も近しい同盟国が自らを守れないようにするというおかしいことを止め、最低限イギリスやフランスのように核兵器を共同保有する団体をアジアに作ることなどができるはずである。
イギリスは常に、如何なる時期においても1隻のヴァンガード級原子力潜水艦を航行させていて、8つのトライデント核ミサイル(その中にはまた8つの独立した核装置がある)を持たせている。イギリスは安全であるが、たった一つの原子力ミサイル潜水艦では戦争を起こせない。日本、韓国、台湾も同様なものを持つべきであり、平和を保つには体系立ってこれを行うべきである。なぜやるべきかを説明し、実行すべきである。これを通じて、核兵器拡散を制御することは可能であることを示し、核の傘がさまざまな国に恩恵をもたらし、そして中国に対して、(核)戦争を起こすことが自殺的であることを強く見せつけるべきである。
上記が私からのもっともオリジナルで推奨する処方箋である。この数年、戦争を如何にして遂行するかではなく、平和を保つことを広島でも思い続けてきた。これ以外の方法は非常に危険な「秘密のゲーム」であり、なにが起きるのかが分からない。最低でも、何が起きているのかを分かりやすくする必要がある。
このほかにも、東アジアにおいて一国対一国の同盟関係ではなく、さまざまな国を巻き込んだもの(インドや台湾も含めて)にしなければいけない。しなければ、何もないのも当然だ。このような同盟体系を作れば、NATOのように長期的な視線で準備や相談が行え、一国と戦争を起こすことは同盟国すべてと戦争をするのと同然であることを、はっきりすることができる。これらの方策が、中国との大規模な戦争を未然に防ぐことに役立つ。ただし、より小規模な紛争はあるだろう。中国は小さなマッチをさまざまな人に配っているため、どれかに火がつくのを避けられるとは思えない。意図的にやっているかどうかはわからないが、わかりやすいのは台湾に対する数回にわたる軍事作戦だろう。我々は台湾を守ることをはっきり言うべきだ(我々が守る行動を見せなくても日本が駆けつけるだろう)。中国の弱点は台湾に対して兵站線を、海峡を通じて維持することであり、兵站の集約点をつぶすことについてはさほど難しいことではない。戦争の可能性も防ぐだろう。これを実現するには、現状ではまだ無理ではあるが、さまざまな分散されたプラットフォームと、より高度な作戦速度が必要である。イギリス、フランス、ドイツが入ってくるのも非常に心強い。
我々が覚えるべきことは、インド・太平洋にかけての戦争の破壊的な影響は、想像を絶するものになるだろう、ということだ。人類根絶を目指すのではない限り、これは狂気の沙汰である。どこかの誰かが必勝必殺の暗器(中国語では殺手賤。ドイツの復讐兵器ヴンダーヴァッフェンが思い浮かぶ)を持っていると思っているかもしれないが、これは毒に満ちている夢である。これの帰結は幾億の死を築くだけである。分散された核兵器はこのような妄想を止めるのにてきめんなのである。
アーサー・ウォルドロン 2019年某日
(宮城宏豪 訳)
(この評論は6月12日に執筆)
カテゴリー
最近の投稿
- イラン爆撃により中国はダメージを受けるのか?
- Internationalizing the Renminbi
- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する
- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か
- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ
- 記憶に残る1月
- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機
- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ
- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?
- A January to Remember